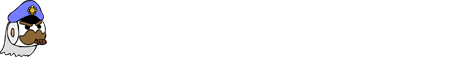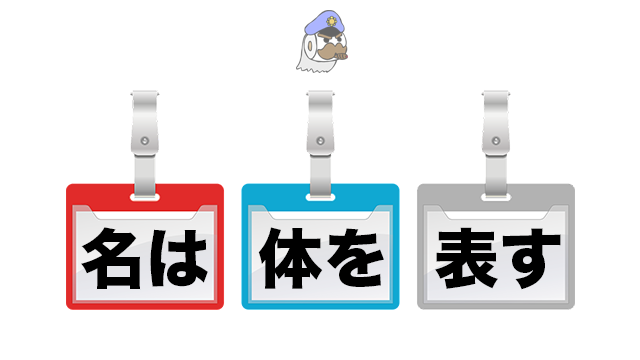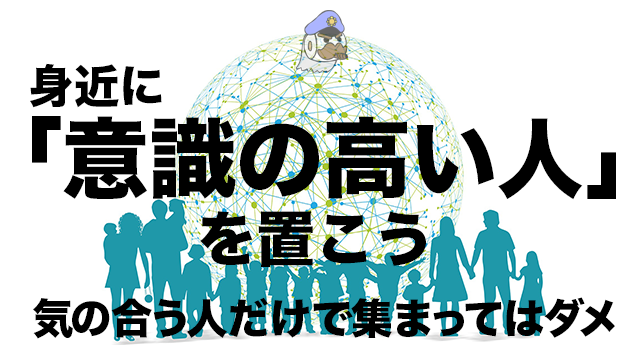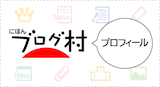・広報という仕事の本当の姿
・パネルディスカッションの進行役に求めらること
・進行役を上手くやり切った3つの理由
おはーん、ペーパー先生です。
先日、仕事でパネルディスカッションの進行役を務めました。
このブログの内容はラジオでも解説しています。
人事部門からの依頼があって引き受けたもので、
先生自身はその道のプロでも何でもありません。
元々、広報畑での経験がありますから取材を受ける機会は山のようにありました。
ただ、聞かれたことに答えるのと、パネラーの魅力を引き出す進行をすることは、
似て非なるものです。
そうそう。本題とは逸れるのですが、広報の仕事は
ドラマで登場する際にはキラキラした憧れの職種という描かれ方をしていますが、
実際はドロドロした現場です。(笑)
多くの方は、会社や商品・サービスのことについて、ペラペラと
インタビューなどで話しているようなシーンを想像されるかもしれませんが、
実際は、すべて事前に作成したQ&A原稿があります。
Q&Aは、関係者からヒアリングを行い、会社としての見解をまとめた回答案ですから、
広報担当者が本人の個人的な見解を記者に述べることは一ミリもありません。
なぜならば広報というのは言葉を持たない法人の代弁者でしかないからです。
入念にQ&Aを作成し、頭に叩き込んで、それをあたかもその場で考えて
話しているかのように、メディアの前で喋る。
しかも、言ったことがそのまま記事なるわけではなく、取材している記者側の
都合の良いように切り取られますから、切り取られた先でどう掲出されるかを
見越したコミュニケーションが必要になる。
これが広報の仕事です。
泥臭さが少しでも伝わったでしょうか。(笑)
さて、話を戻しまして、つまりこうした経験と
パネルディスカッションでの進行では、役割も求められるスキルセットも
まったく違うわけなのですが、イベント実施後に行った参加者へのアンケートでは
すこぶる評判が良かったようです。
パネラーに対する感想に紛れて、
進行の良さを高く評価いただくコメントもありました。
複数人が登壇するパネルディスカッションでは、
・話を振る順番。
・登壇者の話を受けての切り替えし。
・登壇者間での意見交換への誘導。
・参加者と登壇者との繋ぎ。
・議論を深堀するための話題作り。
・トラブル対応。
・時間配分。
この辺りをすべて一人で切り盛りしなければいけません。
ではなぜ先生は、やったこともない進行をそつなくこなせたのか。
理由は3つあります。
①SNSの情報発信
1つ目は、日々のSNSによる情報発信です。
かれこれ1年以上毎朝、音声配信を続けています。
内容はブログで取り上げたことをほぼそのまま紹介しているだけなのですが、
頭の中にある考えを文章に落とし込む。
↓↑
文章にしたものを声に出して読み上げる。
この行き来をしながら構成の見直しもしていきます。
シンプルにたったこれだけのことなのですが、
文脈を整理して、きれいに分かりやすく、相手に伝える意識や技術が相当高くなりました。
②SNSのコメント
2つ目は、好きなインフルエンサーのアカウントに対し、
必ず内容に対して感じたことを、コメントするようにしていたことです。
ツイッターやYouTubeなどでほぼ毎日やっています。
その多くが投資に関する話題ですが、第三者の考え方を受けて、
自身ではどう感じたのかを、その瞬間に文字にまとめて発信をしています。
元々は自分自身の考える力を養うために始めたことでしたが、
これを繰り返していたことで、パネラーが話した内容に対し、
自身での感想、関連する話題の引用など、瞬時に会話の中に織り交ぜながら、
次の話題に移っていくことができるようになったというわけです。
③タモリさん
3つ目は、パネラーの良さを引き出す部分の学びを
かつてのバラエティー番組「笑っていいとも!」の人気コーナー、
「テレフォンショッキング」から学んでいたということです。
先生は物心付いた頃からこのコーナーが大好きでした。
毎日、ほぼ面識のない著名人を招いてトークで20分ほど盛り上げていく。
これを司会のタモリさんは実に31年半もやり続けてきたわけです。
自分自身が目立ってはダメ。あくまでゲストが主役。
相手のちょっとしたコメントをヒントに、
広げられそうな話題を探していく。
見つかったらそこを全力で引き出していく。
そんな姿勢や技術を、先生はタモリさんから学んできたわけです。
もちろんこの番組に限らず、対談や討論番組などを見聞きすることは
とても勉強になるということも付け加えておきます。
さいごに
ということで、先生がいきなりの進行役を見事に努め切った理由を
3つに分解してお話してきました。
確実に言えることは、
長年続けてきた行動は無駄にならないということ。
その蓄積はいつどんな時に役立つかは分からないということ。
まさに「継続は力なり」ですね。
では、ごきげんよう。
よろしければこちらの記事もどうぞ。



優れた力というのは、複数の経験値の組み合わせの上で成り立つ。