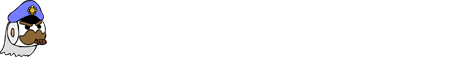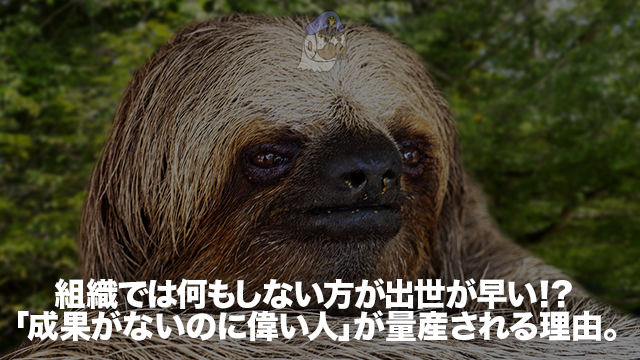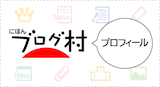・投資ではなく投機と見なされるビットコイン
・“不完全性”が資産運用や人生においてなぜ大切か
・イチローさんの言葉や逆さ柱の逸話から学べること
ごきげんよう、ぺいぱです。
このブログの内容は動画でも解説しています。
今回のテーマは「ビットコインの保有理由」ですが、暗号資産(仮想通貨)への勧誘でもなければ、価格予想が目的でもありません。ぼくがここで話したいのは、「不完全性こそ長続きのコツ」という視点を、ビットコインのような投機性の高いアセットを取り入れることで実践しているということです。
暗号資産の世界はボラティリティが大きく、金融商品としての安定性に欠ける側面があるため、初心者の方や守り重視の方に推奨しづらいというのは言わずもがな。そのため、ここでは「投資」という言葉を使いつつも、実際にはビットコインが“投機”要素の強い商品である点をあらかじめご承知ください。
にもかかわらず、なぜぼくがビットコインをわざわざ持っているのか。今回はそこを紐解くと同時に、「不完全なものをポートフォリオに取り入れる意義」についてお話ししていきます。イチローさんや徳川家康さんの例を挟みながら、人生や資産運用にも応用できるヒントをご紹介していきます。
投機と投資、そしてビットコインの立ち位置
ビットコインは「暗号資産」「仮想通貨」と呼ばれ、誕生からまだ15年ほど(2009年登場)と歴史が浅い資産クラスです。法定通貨として認められているわけではなく(エルサルバドルのような例外はありますが)、長期的な価格安定も見込めません。こうした不確定要素が「投資ではなく投機」と見なされる大きな理由です。ここで改めて投資と投機の違いをおさらいしておきます。
<投資と投機の違い>
投資:価値を生み出す資産を購入し、そこから生まれる利益を得ることを期待する。たとえば、不動産を買って賃貸収入を得たり、株式を買って配当金を得たりなど。
投機:資産自体が生み出す価値ではなく、価格の上げ下げだけに注目して売買する。FXや株式のデイトレード・スイングトレードなどが典型例。
では、ビットコインはどちらなのか。保有しても利子や配当金を生み出さず、埋蔵量が限られているからこその価値を持つゴールドに近いと言われることが多いです。著名投資家ウォーレン・バフェットさんが「ビットコインには本質的な価値がない。何も生み出していない」と繰り返すのは、この投機性に対して強く懐疑的だからです。
一部ではレンディング(貸暗号資産)による利回りサービスもありますが、仕組み自体が複雑でリスクも高く、そもそもビットコイン本体が価値を生み出すわけではありません。こうした背景から「投資」というより「投機」と位置付けられがちなのがビットコインです。
2018年1月の大暴落と300万円の損失
ビットコインを含む暗号資産は、2017年末頃に大きなバブル的上昇を見せました。しかし、2018年1月にかけて急落し、多くの個人投資家が資産を失う結果に。ぼく自身もこの暴落により「2週間足らずで300万円を溶かした」という苦い経験があります。
<ぺいぱ史上最大の運用損失>
当時のぺいぱは暗号資産の将来性というよりも価格の爆発力に熱狂し、手に入れた冬のボーナスを全軍突撃。短期急騰を期待して草コインを大量に買い付け、あれよあれよという間に価格が暴落。含み損が膨らみ、結果として300万円以上を2週間ほどで失う。ここからは蛇足だが、実は心の痛みは数万円ほどの含み損の方が大きい。この300万円損失事案は、あまりの大きな痛手を心が受け止められないことを脳が察知し、忘れようと記憶から消し去ってくれたのでは、というのが個人的見解(笑)
まぁ、そんなことがありながらも、2021年9月に再びビットコイン(1BTC)とイーサリアム(1ETH)を保有し始めました。オルカン(全世界株式)をコツコツ買い続ける“つまらない投資家”なのに、なぜあえてビットコインに戻るのか? ここが本題につながります。
オルカン一本化だけでもよかったのに、なぜビットコイン?
ぼくは2021年6月まで米国や中国の個別株で運用をしていましたが、銘柄管理や決算短信の読み込みに手間を感じ、すべて売却。オルカン(全世界株式)と日本円に集約しました。その方が圧倒的にシンプルだからです。
オルカンは現代ポートフォリオ理論の観点でも、もっともリスクが分散されるインデックスファンド。しかし、この“合理的過ぎる”ことは想定外の大事変に対して柔軟さを欠く懸念もありました。それはどういう事なのか。
<日光東照宮・陽明門「逆さ柱」の例>
・「ひふみ投信」でお馴染みレオス・キャピタルワークスのファンドマネージャー藤野英人さんが語るエピソードに、日光東照宮・陽明門にいくつかある柱の中で1つだけ逆になっている“逆さ柱”がある。“あえて完成しないことで持続させる”ということを象徴する話。
・家康さんが意図していたかどうかは諸説あるものの、「不完全性をわざと残しておくほうが結果的に長続きする」というアイデアは、投資のポートフォリオにも応用できると藤野さんは言う。
ぼくは、余剰資金をオルカンに投資して、あとはほったらかしておくのが個人投資家にとってベストなのだと今でも思っています。そこにあえて“逆さ柱”のような異色のアセットを入れること。これは、変化に対応する余地が生まれるから。ぺいぱにとってのビットコインはそんな役割を担うわけです。
イチローさんの言葉:不完全だからこそ進み続けられる
有名なエピソードとしてイチローさんが先日、記者投票で決まる米国野球殿堂入りを果たした際、イチローさんに投票しなかった記者は394人中わずか1人でした。このことを記者会見で問われた彼は「1票足りないというのは、凄く良かった。不完全だからこそ進もうと思える」という趣旨のコメントを残しています。
<人は不完全だからこそ努力を続けられる>
完全無欠の状態ならもう成長の余地がない。考える余地がない。だから逆に言えば、不完全性を抱えていることが“進化の原動力”になるという考え方。
あまりに完璧な構成を目指すと、自分が想定していない変化に対応できなくなる恐れもあります。イチロー流に言えば、「100点満点ではない」という事実を受け止める姿勢こそが、長期投資をする際の必要な心構えになるとも考えることができます。
不完全性が生む“長続き”とはどういうことか
「不完全性が長続きのコツ」というのは、逆説的に聞こえますが、このようなロジックで成り立ちます。
<完璧主義は柔軟性を奪う>
すべて理想通りにしようとすると、多様なシナリオに対応しづらくなる。たとえば自分の信頼する銘柄や商品を1つだけ抱えるのではなく、評価にバラつきのあるいろんな資産を持つほうがいいと言われるのも、多様な環境変化に耐えるため。
<異質要素が思わぬ救いになる>
コロナ禍のようなパンデミック、中央銀行の予想外の施策、著名人の驚くような発言、優良企業の不祥事など、まったく読めない事態が起きると、通常のポートフォリオでは対処できない面がある。ビットコインのような異端がプラスに働くこと「も」ある。
<“逆さ柱”が組織や投資を救う>
全体が整然としすぎると、大きな衝撃に弱い。わずかな不備・穴・違和感をあえて残すことで、想定外の変化に適応する空間が生まれる。
つまりぼくのビットコイン保有は、“世界中の株式に分散してリスクを抑える”オルカン一本槍が完成形に見えるのに対して「ちょっと逆さ柱を残しておきたい」と意図的に崩しているわけです。
ビットコインが持つ“違和感”の具体例
投資の王道とも言われるインデックス運用とは正反対に位置するビットコイン。何が“違和感”を体現しているのでしょうか? これらの要素が挙げられます。
<値動きの激しさ(ボラティリティ)>
平均して年に数十%、時に数百%レベルの上下動があり、株式市場の変動幅をはるかに超える。オルカンのような安定分散とはまったく違うリスク特性。
<生み出す価値が不透明>
ビットコイン自体は利息や配当を生み出さず、「希少性」や「ブロックチェーン技術への期待」が価格を支えている。いわば“純粋な投機オブジェクト”。
<法整備や社会的認知が完全ではない>
米国での現物ETF承認や一部地域での法定通貨化などが進んでいるものの、規制は途上であり未成熟。“まだ完全に整っていない”という面をまるごと抱えた資産。
ぺいぱのビットコイン保有ルール
では、投機性の高いビットコインをどう扱っているか。ぼくなりの簡単なルールをまとめてみます。もちろん皆さんに勧めるものではありません。
<1BTC・1ETHだけを買って“忘れたことにする”>
・2021年に1BTCと1ETHを買い、追加買付せず放置。
・値動きが激しいのであえて“ないもの”と考え“コア運用のオルカン”に集中。
<税制やリスクを理解する>
・暗号資産の税制は雑所得扱い。そのため現時点では短期トレードにむかない。
・ハッキングリスクがありウォレット管理や取引所選びなどを十分考慮する。
<全体ポートフォリオの数%にとどめる>
・ビットコインの保有比率は、資産全体の10〜20%以下ぐらいが望ましい。
・コア(オルカンや現金)資産をどっしり腰を据えて運用していることが大前提。
「不完全な存在」だからこそ“なくなってもよい枠”として保有する。全損リスクを飲み込む。こうした自分ルールを守れば、ビットコインが大暴落してもダメージは限定的ですし、逆に急騰すればポートフォリオ全体にプラスを与える“スパイス的役割”を果たしてくれます。
不完全性のメリット:組織運営・人生観にも通じる
不完全性の強みは資産運用に限りません。ぼくはかつての勤務先で開発部門長を務め、複数のプロジェクトリーダーをまとめるいわば“ポートフォリオ・マネジメント”のような仕事をしていました。メンバー全員が自分の理想どおりの布陣だと一見完璧に見えますが、実はそれが大きな落とし穴になることもあります。
<異端を排除するとイノベーションが生まれにくい>
個性や違和感を持つメンバーを“面倒だから”と外すと、思わぬブレイクスルーを起こすチャンスも消えてしまう。
<危機的状況で想定外の力になることも>
全員が同じタイプだと、弱点も同じで一斉に倒れる可能性も。異質な要素が混じっていれば、別方向から問題を解決できるかもしれない。
この「異質な逆さ柱」をチーム内にあえて存在させることで、柔軟性や環境変化への適応力をもたらすとぼくは考えています。
イチロー&家康の共通点:「完全」になろうとしない姿勢
イチローさんの言葉や、徳川家康さんの逆さ柱の逸話は、一見関係のなさそうな歴史とスポーツの話ですが、“不完全さがあるからこそ成長が続く”という点で共通しています。
<1票足りなくて良かった話>
殿堂入り投票で満票を逃したことを「不完全だからこそ進める」という捉え方をするあたり、イチローさんらしい哲学。人間の進化において完璧な状態など存在せず、常に課題がある方が前を向けるという発想。
<逆さ柱が長寿命を生む>
陽明門の逆さ柱は「完璧に作り上げるのではなく、あえて一点だけ不完全にしておくことで永続性を願う」という伝説的な解釈がある。完璧を作ろうとするとどこかで破綻が起きるかもしれないが、不完全な余白が適応や変化を可能にする。
ぼくがビットコインを敢えて持つのも、完璧な分散投資に見えるオルカンだけにせず、“もうひとつの可能性”を残す行為と捉えると、逆さ柱の発想と重なります。
「不完全性こそ長続きのコツ」の実践
資産運用においても、人生においても、完璧を目指すと却って脆さを抱えることがあります。ぼくはそれを強く感じるため、ビットコインのような“投機枠”をわざと残し、このように位置づけています。
<失敗を無駄にしない>
2018年1月に300万円を失った大失敗は、自分が長期投資に発想を切り替えるきっかけにもなった。ビットコイン保有はそこで得た教訓を忘れないように背負う重い十字架でもある。
<オルカン一本槍を補完する異端のサテライト>
全世界株式という“王道”をコアとしながらも、想定外の市場変化に備え、爆発力も投機性も高いビットコインをあえて混ぜておく逆さ柱戦略。
<不完全だからこそ楽しめる>
ビットコインは価格の動きが読めず、配当もないが、それこそ投資のロマンやサプライズを内包しているとも言える。“完全分散”の心地よい安定に、少しの刺激を与える存在。
おしらせ
キャラクター”ぺいぱ”がデザインされた「資産運用学園やわらか中学校」公式アイテムがついに販売開始!トイレットペーパーを模したキャラデザの由来は、古くなったお札が再利用されてトイレットペーパーになることや、ウン(運)がつく縁起ものだからなど、諸説あり。いずれのアイテムも日常使いできるシンプルデザインです!ぜひお買い求めください!

さいごに
今回は「ぺいぱがビットコインを保有する理由:不完全性こそ長続きのコツ」をテーマに話を進めてきましたがいかがだったでしょうか?
<ビットコインは配当を生まないし、本来は投機性が高い>
その意味で「投資」よりも「投機」と言われることが多い資産。バフェットさんをはじめ、一部の著名投資家が敬遠しているのも事実。
<あえてポートフォリオに異端を残すことで、“完璧”を崩す>
家康さんの逆さ柱やイチローさんの話などから、むしろ足りないものを抱えたほうが進化や柔軟性を発揮しやすいと考える。
<人生や投資で“もう余白がない”ほど完璧を求めると、逆にリスクが増す>
ビットコインの大きなボラティリティが時には救いになる場面も考えられるかもしれない(もちろんダメージになるリスクもありますが…)。
最後に繰り返しますが、これはビットコイン投資を推奨する話ではありません。不完全性は必要ないと考える人もいるでしょうし、必要だとしてもそれがビットコインである必要もありません。今回は、あくまでぼくの経験と哲学を基に、「わざと不完全性を残すこと」の意味を投資と人生に照らしながら語ったものです。
皆さんも、ポートフォリオを組むとき、組織やチームを作るとき、或いは生き方を設計するとき、“完璧を目指しすぎない”選択肢を考えてみるのはいかがでしょうか。人は不完全だからこそ進める。この考え方が皆さんの資産運用や生活に少しでもヒントになれば幸いです。
人生はノーコンティニュー!悔いのないようにやっていきましょう。
では、ごきげんよう。
完璧を求めすぎると脆くなる。