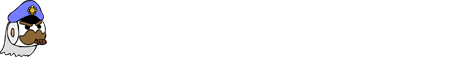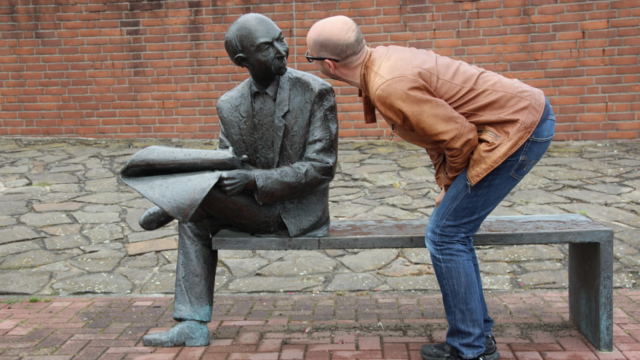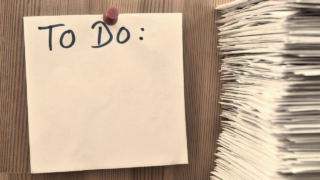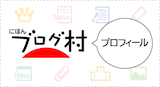・ぺいぱの紆余曲折
・ぺいぱの純資産推移
・ぺいぱとマラソン教訓
ごきげんよう、ぺいぱです。
このブログの内容は動画でも解説しています。
ぺいぱが資産形成を意識して取り組み出したのは2020年で割と最近なのですが、お金を現金以外に使っていくという観点でいくと2004年に当時のマネックス・ビーンズ証券に口座開設して日本の個別株投資を始めた時に遡ります。「お金を育てる」というよりも「株式投資やってると何かカッコイイ」「お金を使ったオンラインゲーム」みたいな感覚だったことは、まさに若気の至りです。
その時点からを改めて振り返ると、たくさんの紆余曲折があったわけですが、結果論として良かったこと・悪かったことに分けるとこんなことが言えます。
<✌️良かったこと>
・家計簿アプリとクレカ決済による支出管理(2014年)
・貯蓄率をゼロから一時6割まで上昇させる(2020年)
・コア資産をオルカンに一本化(2021年)
・サテライト資産にBTCを導入(2021年)
<🤕 悪かったこと>
・日本の個別株での遊び感覚デイトレ(2004年)
・草コインへの全軍突撃による爆損(2018年)
・ハイパーグロース株全振りでコロナショック突入(2020年)
・よく考えずに加入した養老保険での解約損(2020年)
以前にこちらの回「結局フルFIREにはいくら必要なのか?」でも詳しく紹介していますので、よろしければぜひご覧ください。

ぺいぱはそもそもがズボラな性格ですから、常に襟を正して生活をしているわけではありません。そんな人が純資産ベースで億り人に到達するわけですから、色々と運も良かったんでしょう。一方で、こうやって見ていくと良くも悪くも節目節目でそれなりに大きな判断してきてるんですよね。
手元の表計算ファイルで最古の統計が残る2017年末から見た純資産推移をチェックしてみましょう。アセットクラスは商品の中身こそ変わっていますが中核を占めるのは株式・暗号資産・不動産・現金ですから、現在に至るまで大きくは変わっていません。
2017年末:2,002万円
2018年末:2,026万円
2019年末:2,649万円
2020年末:3,829万円
2021年末:4,919万円
2022年末:5,517万円
2023年末:7,314万円
2024年末:1億183万円
※数字は四捨五入
こうやって見ると明らかに2020年から数字の上昇が大きくなっていることが分かると思います。基本的には会社員としての稼ぎが大きく寄与しているわけですが、収支管理や運用精度を高めていったことが資産の増加ペースを加速させてきた、そして現在を形作っていることは間違いありません。そして、ここで得た実体験をまとめていこうというのが今回のテーマとなります。
自身の半生を振り返るのにも近いですから、ここに来るまでの色々な気付き、試行錯誤してきた結果報告でもあります。今このタイミングでそれを改めて文章化してみますと「シンプルにこういうことだな」と整理や腹落ちすることができました。まさに、資産形成の成功と失敗を分けるポイントが何であるかです。
すでに資産形成に取り組まれている方にとっては当たり前で退屈な話になってしまうかもしれませんが、大事なことは繰り返し伝えていくことがこれから資産形成に取り組む方のためにもなりますし、それがこの「やわらか中学校」の役目でもあるなと思いますので、今回は初心に戻ってやっていきたいと思います。
ぜひ最後までお付き合いください!
① 収支を把握しているかどうか
② 貯蓄率を改善する意思があるかどうか
③ お金を運用に回しているかどうか
④ 支出負担の大きい趣味があるかどうか
⑤ 金銭感覚の近いパートナーであるかどうか
資産形成の成功と失敗を分ける5つのこと
最初はこれになりますね。そもそもお金の出入りを見える化していないと、何をどうすれば良いのか手がかりが掴めません。暗闇の中で出口を探すようなものです。
最低限「いま何歳で、いくらあって、それをいつまでに、何のために、いくらにしたいのか」という点を明らかにしない限り、着手する順番や内容が導き出せません。
例えば、
💁♂️Aさん:
30歳独身。資産ゼロで、定年を迎える30年後には趣味の旅行に使うため2,000万円にしたい。
💁♀️Bさん:
30歳独身。資産は現金300万円で、5年後に結婚後して自宅購入するため2,000万円にしたい。
こんな状況の2人がいたとしましょう。一見するとスタートもゴールも似ています。しかし貯蓄をしてきたBさんとそうではないAさんでは、まずやるべきことが変わります。
Aさんの場合は先ほど触れたように収支の把握をし、支出削減・収入増加を計画し、その上で余剰資金を運用に回すという家計の大改革が必要になります。以前のぼく自身が近いステータスでした。なお、旅行も国内なのか海外なのか、どのぐらいの頻度で行きたいのかなど、この2,000万円に妥当性あるのかも要検討ですよね。
Bさんのケースでも同じ流れを抑えたいですが、それなりに貯蓄実績もありますから、そこをこねくり回すよりもアセットクラスの分散状況の再点検や、将来的に購入する自宅の物件選びや買い方などに、より比重を置いて検討した方が良いと考えられます。特にパートナーがいる場合はお相手の価値観や意向も十分汲んでいく必要もありますから時間を要します。
家計簿をつけていない場合、多くのケースでは「銀行の預金残高しか分からない」となります。勤務先の給料が入ったら1ヶ月の間でほとんどを使ってしまう、なんていうのはまだ良い方。将来の自分には迷惑をかけるでしょうけども、他人には迷惑かけないからです。
一方で、カードローンなどの借金があるような場合だと話が変わってきます。他人に迷惑かけることはもちろんですが、最悪のケースでは借金がいくらあるのかも把握できていないということもあるでしょう。お金の増やし方に必要なアクションで優先順位があるように、借金の返し方も金利が高いものから着実に借入元本を減らしていくことが定石。この辺のお作法を知らずに散発的に返済をしているとものすごく非効率になっているなんてことも起こり得ます。
社会人になって借金を背負っているケースで最も考えられるのは奨学金ですね。ただこちらの場合は無利子のものもありますし、有利子(貸与型)のものでも利率はかなり低めに設定されているケースが多いですから、計画を立てれば資産形成を軌道に乗せることはできます。現に、そうした返済を乗り越えて資産形成に成功されているYouTuberやブロガーの方はたくさんいらっしゃいますよね。
なんやかんやと話をしてきましたが、要は状況によって戦い方はまったく異なるということです。ぼく自身の経験でいけば、2020年のおうち時間で極限まで支出削減に取り組みましたが、そこで役に立ったのはスマホの家計簿アプリでした。
貯蓄率ゼロだった2014年から「マネーツリー」を使い始め、ここに記録を残すために支出のほとんどをクレジットカード決済に集約してその後の生活を送っていたことが、支出改善にとても役に立ちました。なので、極論ではありますが支出改善のやる気は無かったとしても、収支の見える化を自動化しておくことはすごく大事。将来の自分を救います。情報がないと戦いようがありませんからね。
あと、今回はゴール設定のあり方については詳しく触れていきませんが、この回『正しく知れば成果が出る!「目的」「目標」「手段」の違い』が参考になるかもしれません。ちょっと古い回ですが今でも十分役に立つかと思います。

そんなわけで、資産形成の成功と失敗を分けることの1つ目は「収支を把握しているかどうか」でした。
資産が増えるのも減るのも、この方程式次第です。
<資産の方程式>
(収入 - 支出) + (資産 × 運用利回り)
フロー ストック
「やわらか中学校」ではよくご紹介していますが、資産形成においてもうこれが全て。①はここに入れていく数字を見える化しようという話でしたが、この項目では方程式前半の「フロー」に着目していきます。
お金を増やしていくためには収入から支出を除いた額をどれだけ大きくできるかにかかっています。つまり収入を増やすか、支出を減らすかをしていく。言葉にすれば実に簡単なことですが、実生活をしているとなかなか難しい。
順番としては支出改善から行う方が理想的です。収入を上げていくよりは簡単に結果が出るからです。1つ500円のコンビニスイーツを我慢したら、その月は従来よりも500円貯蓄が増えます。しかしながら、新たに500円多く稼ぐとなるとこれはなかなか骨が折れます。会社員の給料を増やしたり副業を開始したりするのは即効性に欠けるわけです。なので支出削減で目に見える効果を出し、モチベーションを高めた上で収入アップの行動も組み合わせていくというのが鉄板でしょう。実際にぼくもそうでした。
どの程度のお金を残すかという点をよりシンプルに示すために貯蓄率という数字があります。貯蓄率とは貯蓄額を可処分所得で割った比率です。例えば
💁♂️Aさん:
収入500万円 支出450万円 =貯蓄率10%
💁♀️Bさん:
収入400万円 支出250万円 =貯蓄率37.5%
このように、稼ぐ力が足りなくても、貯める力が上回れば貯蓄率では勝つことができます。資産形成における足腰は、=収入と支出の差をどれだけ広げることができるか、というわけです。ここに面白みややる気を感じることができるかどうかというのは、資産形成の成功可否に大きく関わるとぼくは思います。
ぺいぱは2020年、このモチベーションに火がついたことが、その後の資産形成を大幅に加速させていくことになりました。貯蓄率推移を見ていきましょう。
<🐷貯蓄率推移>
2017年:27.39%
2018年:41.48%
2019年:7.36%
2020年:59.98%
2021年:60.57%
2022年:44.21%
2023年:23.69%
2024年:34.01%
推移で分かる通り、2020年・21年と貯蓄率6割というところまで急激に引き上げたことで、大きく投資原資を生み出すことに繋がるわけです。冒頭での純資産推移でも2020年以降その伸びが加速していることにもつながります。
「数字にする」というのは見たくないものを目にすることにもなりますから、最初は気が乗らないかもしれません。ただ、数字であることが逆に闘争心に火をつけることにもなるわけです。人は前に進んでいる実感がある間はその歩みを続けやすいもの。逆に進んでいるのかどうかがよく分からなくなるとやる気を失います。これは資産形成に限らず仕事でも趣味でも勉強でも同様ですね。
そんなわけで、資産形成の成功と失敗を分けることの2つ目は「貯蓄率を改善する意思があるかどうか」でした。
②では資産の方程式の前半部分を取り上げました。収入から支出を除いたお金。このお金の中ですぐには使わなくても良い余剰資金を運用に回していく「ストック」がこの項目での話となります。
「自分だけではなくお金にも働いてもらう」
資産形成を加速させることができるか否かは、この概念を持てるかどうかとも言い換えることができます。もちろん、運用に回すことをしなくても多くの資産を築くことは可能です。現に昭和世代の方々はそうやって財を成してきた人が多かったことも事実です。しかしそういう方々と現役世代とを比べた場合、我々は相当な向かい風の中で同じ競技をしていることを認識した方がいいですね。
現役世代を昭和で過ごしてきた方々は、高い金利やバブル景気の中にありました。郵便貯金や銀行預金で金利6%、7%なんて時代です。しかもバブル崩壊後も長らくデフレでしたから、物の価値がどんどん下がっていく。つまりお金を持っていることがある意味で正解の時代でもありました。
それが現在では超低金利。そしてインフレにも突入しています。物の価値が上がっていくスピードに収入が追いついていかない、なんていうことも受け止めて生きていく必要がある。つまりどれだけ支出削減し、収入増を目指して取り組んでも、豊かにはなっていかない可能性が高い。令和に生きる現役世代はテレビゲームでいうところのハードモードで戦っているわけです。
そんな時、主人公はアイテムを使ってパワーアップし対抗するものです。それが資産運用なんですね。自分の代わりにお金を稼ぎに行ってくれる分身のようなもの。
・「パーマン」でいうところの「コピーロボット」
・「グラディウス」でいうところの「オプション」
・「ガンダムF91」でいうところの「質量を持った残像」
つまりはそんなことです。これまでは自分一人の力でお金を稼ぐしかなかったところ、自分の分身をつかって二馬力で稼いでいこうじゃないか。これが対抗策だということです。
ただ、自分自身が稼ぐ場合は、会社員としての収入という点で一定の稼ぎが担保されています。しっかり働いたのにその月の給料がマイナスになるなんてことは通常起こり得ません。一方で、資産運用については、出稼ぎに行った自身のお金たちが、稼ぐ時もあればそうでない時もある。場合によっては元本を大きく毀損する場合もある。これが怖いから多くの日本人は一馬力でなんとかしようとするわけです。
資産運用がどうあるべきかにたった1つの答えはありません。どの証券会社で・どんな商品を・そのぐらいの額買うべきか。一人一人最適解は違ってくるからです。日本人は投資と聞くと「個別株」とか「暗号資産」とか「不動産」とかをイメージしがちです。これはぼくもそうでした。何かを1点買いして握りしめる。まさに丁か半かみたいな世界を思い浮かべます。
今回は本題ではありませんから深くは触れませんが、投資は「長期に渡り・国際分散で・低コストに抑える」のが鉄板です。もうここは、前回取り上げた『「オルカン」と「地球の歩き方」のコラボブックがおもろすぎる』を何も言わずまずは一度見てください。
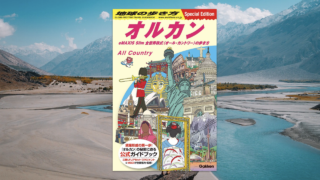
投資は自己責任です。ぼくは特定の商品を勧めることはしませんが、資産形成をやってきた半生を振り返ると、概ね答えは出てるんじゃないかなと思ったりもします。
そんなわけで、資産形成の成功と失敗を分けることの3つ目は「お金を運用に回しているかどうか」でした。
ここまで紹介してきた①〜③で資産形成に重要なポイントはほぼ紹介し終わっているので、ここからは番外編といったところになります。
先ほど、資産形成の順番として「収支の見える化の次に支出削減である」といった話をしました。削減というぐらいですから、年間で発生している支出を一覧にし、その中から「減額」もしくは「全廃」できるものを整理していくわけですね。
ここは個性が出るところですし、やはりただ1つの正解はない。それで良いと思います。結局、どれだけ支出を抑えられても、それで当人の幸福感が無くなったり、健康を害したり、大切な友人を失ったりしては本末転倒です。唯一の正解がない分野だからこそ、ここの匙加減のあり方は=個性でもあるわけです。
ぺいぱも2020年に支出の見直しを行いまして、年間166万円の削減に成功しました。無駄な支出が多かったということや、パンデミックの最中で家にいる時間が多かったこともあるのですが、その後のQOLにはぜんぜん影響ありませんでしたから、うまくいった削減だったと言えるでしょう。こちらの回「ぺいぱが使っているサブスク大公開:今後の削減プランも示す」でも取り上げていますので、ご興味があればぜひご覧ください。

で、ようやくこの項目のテーマになるのですが、どんな趣味を持っているのかで資産形成の捗り方は大きく変わります。例えばこんなことですね。
<💸 お金のかかる趣味>
ゴルフ(道具・プレー代・会員権)
車・バイク(購入費・維持費・カスタム)
カメラ(機材・レンズ・現像代)
楽器(ピアノ、ギター、バイオリン)
釣り(道具・ボート・遠征費)
スキューバダイビング(機材・ライセンス・旅行)
スキー・スノーボード(道具・リフト代・遠征費)
フィギュア・プラモデル(購入・改造・保管)
ワイン・ウイスキー(調査・収集・保管)
海外旅行(航空券・宿泊費)
アート・絵画(収集・保管)
… … …
<🪴 お金のかからない趣味>
読書(図書館・電子書籍の無料本)
ランニング・ウォーキング(靴さえあればよし)
サイクリング(ママチャリでも楽しめる)
筋トレ(自重トレーニングなら無料)
瞑想・ヨガ(マット程度)
日記・ブログ執筆(手持ちのアイテムで)
散歩しながら写真撮影(スマホでOK)
家庭菜園(ベランダや庭の小規模なら低コスト)
料理・お菓子作り(食費と兼ねられる)
囲碁・将棋・チェス(無料アプリで十分)
DIY(小規模なら100均や端材活用)
ボードゲーム(初期投資後は繰り返し遊べる)
ざっとこんな感じでしょうか。
もちろん、どんなことも深くやればお金がかかるし、その逆にお金がかかりそうなことも安く済ませる方法はあります。ここでお伝えしたいのは
「お金のかかる趣味」
=道具依存・場所依存・遠征依存するものが多い
「お金のかからない趣味」
=日常で完結・自分の身体や思考を使うものが多い
という特性ですね。
先ほども「個性が出る」と話した通り、お金がかかるからダメとか、かからないから良いという簡単な話ではありませんし、何を取って何を我慢するのか時間軸で考えることも大事です。今は控えるけど〇〇年後にはやりたいとか。今のうちにこれを体験しておいて将来は別のチャレンジをするとか。若さは失われていきますから、体力・気力があるうちじゃないと行えないようなことを優先するなど、計画的に取捨選択することが求められます。
ちなみにぺいぱの趣味は
・散歩
・YouTube/ブログ運営
・二度寝
このぐらいですから、これが幸せかどうかはさておき、お金はかかりません(笑) ちなみに7、8年前まで、ぺいぱは自分の老後のために、レトロゲームのカセット(主にファミコン・ゲームボーイ・スーファミ)集めに奔走していたことがありまして、これがかなりお金や時間や根性を必要とする分野だったことが思い出されます。
そんなわけで、資産形成の成功と失敗を分けることの4つ目は「支出負担の大きい趣味があるかどうか」でした。
最後はこれですね。よく耳にされる機会あるかと思いますが、離婚原因の上位には金銭感覚のズレというのがよく挙がります。具体的には「低賃金」「浪費癖」「借金」といったあたりです。
お付き合いをしている間は家計が別ですから大きな問題になることはないと思いますが、これが結婚して1つの家庭になるとなれば話は別です。
結婚後は家計を1つにするいわゆる「合併型」を選ぶか、別家計のままにする「持ち株会社型」を選ぶかは好みの分かれるところかもしれませんが、ぼくの周辺で結婚をされている方の多くは合併型で、その管理を奥さまがしているというのがほとんどでした。これ、日本人には最も多いケースでもあります。
そうそう。ぼくの元勤務先には非常に優秀な経営企画マンがいました。ぺいぱ自身も部長職をしていた時にはとてもお世話になったわけですが、そんな彼も家庭では奥さまがお金の管理をしており、自身ではまったく見ていないと言ってました。
ここまで「ひとそれぞれだから唯一の正解はないよね」とお茶を濁し続けてきましたが、この結婚後の家計管理のあり方については珍しく正解があります(笑) それは「収支をちゃんと見れて、運用でお金を育てていけるスキルを持った方が管理をする」です。
決め事という点では、家計担当決めの延長線上でもありますが、将来的に支出管理で大きく数字が揺れる部分、「持ち家か賃貸か」「子どもをどうするか」この辺りの合意形成もしっかりとっていないと、後々困ることになります。そして④で取り上げたような、本人たちが将来的に取り組みたい趣味があるのかどうかなんていうのも大事ですね。
安全策として、すべての不確定要素でお金のかかる方を盛り込んでおくというのが理想ではありますが、そうなると数字が爆発的に膨らみすぎて現実的ではありません。また、こんな重要な点を意思確認しないまま進むことで、それこそ将来大きな亀裂を生みそうな気もします。
独身クソ野郎のぺいぱ、結婚後というのは未知の領域でありますが、彼女がいた時期を振り返ると、デート代は全額負担していました。食事も買い物も旅行もですから、なかなかバカになりません。先ほど過去の貯蓄率を紹介しましたが、2019年以前が低いのはそうした事情もあります。しかしまぁ、彼女と過ごす時間、一緒に食べた食事、相手を思いやる気持ちは、お金に換えがたい価値がありますから、ここで触れるのは適切ではないかもしれませんが。
いずれにしても、一人のときはしっかり資産形成できていたけど、結婚して雲行きが怪しくなった、なんてことは可能性として十分あるわけですので、ちゃんと念頭に置いておきたいところです。
そんなわけで、資産形成の成功と失敗を分けることの5つ目は「金銭感覚の近いパートナーであるかどうか」でした。
おしらせ
キャラクター”ぺいぱ”がデザインされた「資産運用学園やわらか中学校」公式アイテムがついに販売開始!トイレットペーパーを模したキャラデザの由来は、古くなったお札が再利用されてトイレットペーパーになることや、ウン(運)がつく縁起ものだからなど、諸説あり。いずれのアイテムも日常使いできるシンプルデザインです!ぜひお買い求めください!

さいごに
今回は「資産形成の成功と失敗を分けること」をテーマに5つのポイントをお届けしてきましたがいかがだったでしょうか?
① 収支を把握しているかどうか
② 貯蓄率を改善する意思があるかどうか
③ お金を運用に回しているかどうか
④ 支出負担の大きい趣味があるかどうか
⑤ 金銭感覚の近いパートナーであるかどうか
取り上げた内容、特に①〜③については資産形成における基礎中の基礎ですから、この「やわらか中学校」をご覧いただいている方にとっては釈迦に説法だったかもしれません。
基礎であるということは、ここを外さなければどなたでもそれなりに資産形成は進むということです。資産形成はマラソンを走るようなもので、身の丈を超えるスピードで走ってしまうと、その区間だけは記録更新となるかもしれませんが、全区間では最悪の結果になります。もちろん、のんびり走りすぎてもタイムオーバーしてゴールテープを切れないなんてことにもなり得ます。全ての区間で安定したスピードを出すことこそが大事であり、それこそがゴールへの近道にもなります。
そういえばぺいぱ、むかし会社の人と駅伝大会に参加したことあるんですよね。1人5kmを4人で繋ぐ大会でした。国際大会も行われるような大きなスタジアムがスタート地点だったんですが、なんだか気持ちが高揚してしまい、最初の1kmを5分台(普段は7分台)という驚異的なハイペースで走ってしまい、残り4kmをグダグダで終えてしまったことを思い出しました。たしかこの大会に出場したのは貯蓄率ゼロだった2014年だった気もします。何かの暗示だったのかもしれませんが、それが資産形成に生きたのは6年も経った後でした(笑)
ということで、皆さんも資産形成の成功と失敗を分ける要素でこんなのあるよ!ということがあればぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。こういうケーススタディは必ず誰かの役に立ちますから、なんぼあってもいいですね。
この「やわらか中学校」ではお金や仕事に関する話題を中心に、FIRE生活に突入したぺいぱの日常を赤裸々にお届けしています。ぜひチャンネル登録・いいね・コメントをよろしくお願いいたします!
また、サブチャンネル「ぺいぱのひとりごと」は、ぺいぱが興味関心のある話題を取り上げて好き放題喋り倒すラジオのようなライブ配信番組となっていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
人生はノーコンティニュー!悔いのないようにやっていきましょう。
では、ごきげんよう。
人生も建築も開発も資産形成も、基礎が大事。