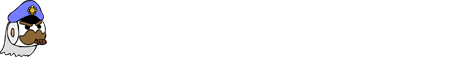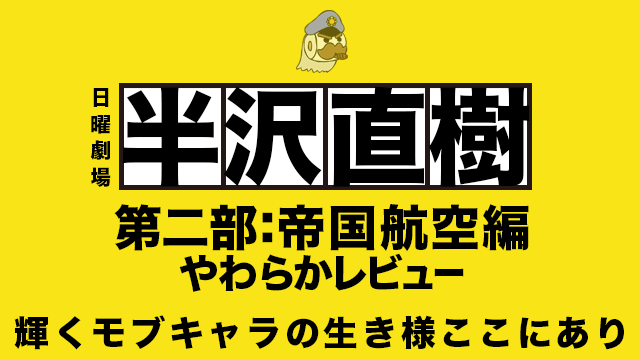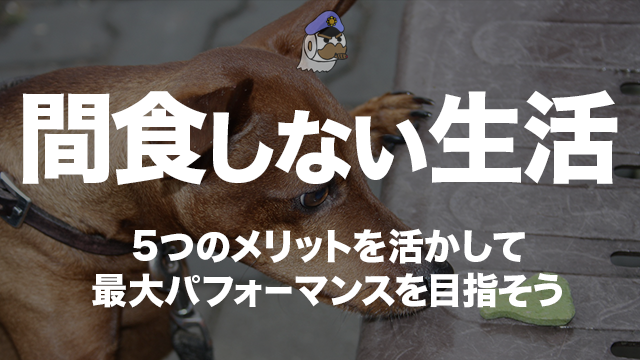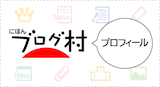・定量的な指標で考えると
・ぺいぱのFIRE時点の資産構成
・必要なのは額より型
ごきげんよう、ぺいぱです。
このブログの内容は動画でも解説しています。
今回は「FIREにいくら必要なの?」というテーマで話していきます。最初に言っておくと、これには1つの明確な答えはありません。独身と既婚、20代と40代、都心と郊外、子なしと子ありなど、置かれた環境によってどうあるべきかは変わるためです。
仮に、ぺいぱとまったく同じステータスにある人物がもう一人いたとして、片方は大胆、もう片方が慎重な性格だったとしましょう。極論ですがこれによっても必要額は変わると思います。
そんなわけで今回話をしていくのは、四半世紀続けてきた会社員を2024年末で卒業し、現在のところフルFIREをしているぺいぱが、7ヶ月ほど経過をした上で結局のところどの程度の資産があれば大丈夫だと考えているのか。これについてです。万人に当てはまる回答を導き出すのではなく、FIRE達成した実体験からどう考えるのか、という考察回となっています。
ぼくはもう時期50代に入る独身男性です。一般的には独身FIRE民は1億円あれば十分とか言われますが、人によっては「それじゃ全然足らない」とか逆に「そんなに必要じゃない」という両極の話も山のようにありますよね。先ほど触れた通り、特定の結論がないからこそ盛り上がるのだとも言えますが、皆さんはどうお考えでしょうか?
ぜひ「自分だったらこのぐらいじゃないかな」なんて想像しながら、最後までお付き合いいただければ嬉しいです。
定量的な指標で考えると
FIREは経済的に自立した早期退職を意味するわけですが、もう少し噛み砕いていくと、「お金に縛られず、自分が本当にしたいことに注力できる時間を確保すること」と言い表したほうがしっくりくるように思います。ゆるく働きながら趣味などに軸足をおくサイドFIRE的生き方が日本では好まれますし、どちらかといえばFIREの主流もこちらのような感じありますよね。
ただし今回はフルFIREを前提に話を進めていきます。労働収入を得ずに資産収入のみで生活を維持していくにはどのぐらい資産が必要なのかということですね。先ほど1億円という具体的な数字を出しましたが、これは「4%ルール」からきているものです。
概要:
リタイア後の資産を安全に取り崩すための指針。米国株式(S&P500)を中心とした運用、米国のインフレ率をもとにした考え方。FIREに向けた必要資産額の算出によく用いられる。
計算式:
年取り崩し額 = 資産総額 × 4%
事例:
リタイア時に1億円の資産を持っている場合、「1億円 × 4% = 400万円」となり、年間400万円を取り崩して生活することが可能。この範囲であれば資産が枯渇することなく長期にわたって生活を支えることができるとされる。年間生活費の25倍という計算でも良い。
多くのFIRE民、そしてFIREを目指している人が一つの指標としているのがこの「4%ルール」です。1998年に米トリニティ大学のグループによって発表された資産運用に関する研究から導かれたもので、米国株式の年平均成長率7%、そして毎年3%インフレが進むという前提を踏まえて「4%」という数字が導き出されています。
もちろんこれは、4%で取り崩していっても資産が目減りしない確率が高いというだけで、それを保証しているわけではありません。何よりも株式は短期的に見れば浮き沈みが激しいですし、今まさにインフレは3%を平気で超えている時代でもあります。そんな中で生きていると、株式の成長もさることながら、インフレ率の将来をどう評価するべきかの方が、自分の生活を大きく左右すると強く思わされますね。
そして日本で生活をしている我々にとっては日本円が必要ですから為替も考慮する必要がある。そうしたことを含めて「4%ルール」すべてを鵜呑みにはできないわけです。
で、ここからわかることは、FIREで大切なのは「資産額」よりも「支出額」だということ。これは当たり前な話ですが、年間支出が100万円の人は2,500万円あれば資産が枯渇しないと考えることができる。だけど400万円の場合は1億円必要になる。数字遊びでしかありませんけども。
ちなみに総務省「家計調査(2023年)」によると、単身世帯の年間支出平均はおよそ202万円(月約16.8万円)とあります。どの地域でどんな水準の生活をするのかにより数字は大きく振れますから、この平均値ほど役に立たないものもないわけですが、仮に年300万円と多めに見積もると4%ルールでは7,500万円。これは、毎月3万円の積立をして年7%のリターンでコツコツ取り組むと39年5ヶ月後に到達する金額です。社会人になってからすぐに資産形成に励んでも60歳を超えてしまうわけですから、4%ルールで見た時のフルFIREというのはなかなか高いハードルだなと思うわけです。
では、ぺいぱ自身はどうだったのか。これを具体的に振り返っていきたいと思います。「早期退職を決断した時」「早期退職をした時」「いま」、おまけとして「記録が残る最初期」の4つのタイミングです。
早期退職を決断した時(2024年6月末時点)
ぺいぱは勤務先を辞めること決断した際、100人ほどを預かる部門の管理職をやっていました。これがなかなかキツくてですね、ある種のギブアップだったわけです。計画的にFIREを目指していたわけではないんですね。詳しくはこちらでも紹介していますので、ご興味があればぜひどうぞ。

退職意向を上司に伝えたのが2024年6月でしたので、その末締めでの資産状況です。なお、資産については純資産で示します。「暗号資産」は1BTC・1ETH。「不動産」の評価額についてはAI査定サービスでの算出価格平均を取っていますので、あくまで目安。負債欄にある「カード払い」というのは確定しているクレジットカード利用額を反映しています。
<資産>
オルカン:5,658万円
暗号資産:1,045万円
不動産: 3,998万円
法定通貨:576万円
—————————
小計:1億1,277万円
<負債>
住宅ローン:▲2,025万円
カード払い:▲45万円
—————————
小計:▲2,070万円
—————————
合計:9,207万円
※数字は四捨五入
年間支出はこの10年でだいたい400〜600万円のレンジです。4%ルールにおける保有資産(つまり米国株式)とぺいぱのそれとでは構成が全然違いますから、当てはめて考えるのはかなり乱暴なんですが、生活スタイルを変えずにいけば資産はいずれ枯渇する計算になります。
一方で、フィジカル・メンタル共に自身の健康を最優先して会社員を辞める決断をした際、この資産規模があったことが大きく後ろ盾になっていたことは間違いありません。これがなければ「休職して復職を狙う」とか「転職活動する」とか、そういう選択をとっていた可能性が大いにあるわけです。
最初期の記録(2018年1月末時点)
ちなみに、ぼくがFIREなんて概念を知らず、貯蓄率もゼロ〜一桁%台を記録していたころの資産額もせっかくなので振り返ってみました。ぺいぱが、B/S(貸借対照表)とP/L(損益計算書)を表計算ソフトでまとめるようになった最初期の記録が2018年1月末です。「養老保険」は当時の解約返戻金の額となります。
<資産>
米国個別株:147万円
中国個別株:64万円
暗号資産:473万円
持株会:424万円
養老保険:286万円
不動産:2,912万円
法定通貨:28万円
—————————
小計:4,334万円
<負債>
住宅ローン:▲2,576万円
カード払い:▲37万円
—————————
小計:▲2,613万円
—————————
合計:1,721万円
※数字は四捨五入
これ、2017年末のボーナスを暗号資産の草コインにほぼ全軍突撃させて、わずか一週間ちょっとで300万円以上の損失を出した直後。あまりのスピードと損失額で痛みすら感じていなかった際の忌まわしき記録です。現金わずか28万円という事実が、全軍突撃感を見事に示していますよね(笑)
ぺいぱが資産形成を始めたのはこの2年半後からですので、資産内容もまったく整理されていません。生き残った「暗号資産」も中身はほぼ草コインですし。
この記録が今から7年半前。40代目前で資産額が2,000万円にも満たなかったんですよね。まぁ、資産形成に意識が向いていない時代でも「こんだけお金があった」と考えるべきか否かは解釈の別れるところですが。
ぼくの場合、2年半後に解約することになる「持株会」とか「養老保険」とか、打ち手として誤ったなと後悔しているカテゴリ、強制貯蓄効果を生んでいたという点は結果オーライでした。やはり、資産形成に意識が向いていない時だからこそ、それが定期預金だろうがなんだろうが、強制的に別のバケツに流れていく仕組みを作っておくことは大きいですね。
早期退職時(2024年12月末時点)
さて、話が逸れてしまいましたが続いては早期退職をした2024年12月末時点の資産状況を見ていきましょう。
<資産>
オルカン:3,738万円
暗号資産:1,519万円
不動産: 3,916万円
法定通貨:1,027万円
—————————
小計:1億200万円
<負債>
カード払い:▲16万円
—————————
小計:▲16万円
—————————
合計:1億184万円
※数字は四捨五入
ぺいぱ、2024年6月に退職意向を申し入れて、そこから9月までは後任が決まらず、10月に有休消化を入った後にも引き止めにあい、ほんといつ辞められるのか全然わからなかったんですよね。なので本来はしておくべきだった引っ越しも、会社員の身分があるうちにできなかったわけです。
ただ1つだけ無職に向けて準備をしたことがあって、それが住宅ローンの完済です。カード払いはいまだに残っていますが、これでほぼ無借金経営。自己資本比率は99.7%ほどで、見事キーエンスを抜いたわけです(笑)
なお、住宅ローンは返済せずにそこで浮いた資金を運用に回していくほうが合理的だとする考え方もあります。これはたしかに金利が上がり始めた今でもそういう考え方はあって良いと思いますが、ぼくは支出コントロールを優先して返済に踏み切りました。この回でも詳しく語っています。

あと、ほんとたまたまではあるのですが、億り人にも滑り込みでなることができました。正確には11月分の給料が入った11月25日(月)に初到達したのですが、月末締めベースでいくと12月末だったわけです。
で、この時にぺいぱが4%ルールのことを意識していたかというと、結論ぜんぜんしていませんでした。「まぁ、辞めてもなんとかなるだろう」ぐらいで。ただし「1億円あれば…」という枕詞が大きく影響していたことも事実です。もう少し分解すると、
・オルカンが4,000万円近くの塊である。
・米国株より成長力が劣る部分をBTCがカバーしてくれる。
・家賃収入が年間140万円ほど入る。
このあたりの要素が「なんとかなるだろう」の源泉になっていたのは間違いありません。
先ほど、FIREにあたっては支出コントロールが重要であるとの話をしましたが、独身ですからここはどうにでもなるわけです。ちょうど、先日ぺいぱが利用している支出を紹介する回をお送りしました。

食費や税金以外の固定費をまるっとサブスクとしてまとめたものです。詳しくは動画を見ていただければと思いますが、金額だけを見るとこんな感じになりました。
<ぺいぱのサブスク年間費用>
■2020年9月時点
年2,549,341円
■2025年7月時点
年4,275,969円(+1,726,628円)
■今後目指すところ
年2,550,585円(▲1,725,384円)
※カッコ内は前回比較
現時点は会社員生活の名残が各種あり、かなり固定費が膨らんでるわけですが、年末までには250万円台まで下げる予定です。ここに食費を加えて300万円ちょっとぐらいでしょうか。この感じを維持することができれば、労働収入がなくても破綻することはないんじゃないかなとは思っています。ま、根拠ないですけど(笑)
いま(2025年7月末時点)
なお、今年に入ってからは支出超先行。特に住民税をはじめとする税金周りですね。ゴリゴリ毎月削られている中での最新7月末時点の資産状況はこのようになっています。
<資産>
オルカン:3,878万円
暗号資産:1,837万円
不動産: 3,980万円
法定通貨:455万円
—————————
小計:1億150万円
<負債>
カード払い:▲33万円
—————————
小計:▲33万円
—————————
合計:1億117万円
※数字は四捨五入
住民税140万円や、それとほぼ同額の保険料支払いを絶賛している最中ではありますが、相場の好調さに恵まれて、早期退職時とそんなに資産額変わってないんですよね。今回紹介したものをまとめるとこうなります。
<ぺいぱの節目の純資産額>
18年01月末時点:1,721万円(最初期の記録)
24年06月末時点:9,207万円(退職意向を伝える)
24年12月末時点:1億184万円(早期退職時)
25年07月末時点:1億117万円(いま)
「額」より「型」
今回は「FIREをするのにいくら必要なのか?」をテーマに話をしているわけですが、ぺいぱは独身ですし1億円あればなんとかなるだろうという肌感覚はあります。事実、このFIRE後の半年間、お金の面で何かを心配したりすることはありませんでした。
ただそれは、1億円という額そのものというよりも、そこに行き着くまで4年半ほどやってきた資産形成の「型」が体に馴染んでいるから、という方がより正しいです。人というのは親元を離れて以降は「資産の方程式」に沿って走り続けます。
(収入 - 支出) + (資産 × 運用利回り)
フロー ストック
この取り組み、ぼくの場合は成功も失敗も含めて肌に馴染んで、いまや感覚的に物事(つまりお金に絡むこと全般)を動かしていけるようになったのだと思っています。息を吸うように行うって表現のほうが近いでしょうか。「ああ、支出が先行しすぎてるな」とか「この利回りならこの額を取り崩すのは大丈夫だな」とか。そういうのを肌感覚でやれる。
特定の数字を決めて自動化するなんて方も多いでしょう。「現金比率」とか「自動取り崩し」などがそうですね。ぼくの場合は、そういうバルブの開け閉めというのを、その瞬間瞬間で反射的に行ってます。で、そういう力を得た人こそがフルFIREの権利を得るとも言い換えられるのではないでしょうか。
ま、偉そうなこと言ってもぺいぱはスボラな性格ですから、常に襟を正して生活をしているわけではありません。でも、さっき言ったようなバルブの開け閉めは人よりも敏感だと思います。定量的な答えがない分野だからこそ、過去の経験則に基づく勘のような力が必要だし、結局FIREするような人はそういうことに優れている。自分の型を身につけている。そんな感じなのでしょう。
なので、仮にぼくの資産が7,000万円であれば7,000万円なりの生活をするでしょうし、5,000万円だとしても同様。だってそれに合わせてコントロールできるから。もちろん一定の水準を下回れば労働収入を得ることを考えるでしょう。それは自分の中でも最低限の生活ラインはあるからです。
なので、FIREを目指して日々資産形成に励んでいる皆さんは、免許を取るための路上教習中だと思ってればいいんじゃないでしょうか。そうしたプロセスにこそ価値があります。資産はどこまでいっても、自分の力の及ばないところで上がったり下がってりしていきます。でも、自分の得た知識とか経験とか能力はずっと活きますからね。例えばぺいぱですとこんなことが血肉になっています。
<🤕ぺいぱが負った傷>
・日本の個別株での遊び感覚のデイトレ(2004年)
・草コインへの全軍突撃での爆損(2018年)
・ハイパーグロース株全振りでコロナショック突入(2020年)
・よく考えずに加入した養老保険での解約損(2020年)
<✌️ぺいぱの英断>
・家計簿アプリとクレカ決済による支出管理(2014年)
・貯蓄率をゼロから一時6割まで上昇させる(2020年)
・コア資産をオルカンに一本化(2021年)
・サテライト資産にBTCを導入(2021年)
なお、少し定量的な話をすると、ぺいぱは先ほどもお伝えしたように、今後しばらくはこのあたりの収支をイメージしていきます。
<年間支出イメージ>
▲350万円
<年間収入イメージ>
家賃:144万円
広告:60万円
労働:60万円
——————-
+264万円
支出は先ほど触れた通りで、年300万円〜350万円のレンジに収めたいですね。収入面では家賃収入のほか、広告というのはYouTubeとブログで月5万円。あとは何か物書きなど在宅でできるような案件を受けて月5万円。やや背伸びしていますがこんな感じを目指せればなと。ま、これを労働収入と捉えることもできちゃいますが、会社員ではないので個人的には「自己実現」とか「他社貢献」の範囲ですね。
で、差分で90万円ほど足が出るわけですが、このぐらいなら運用でなんとかなるんじゃない?と思っています。
ぼくのコア資産であるSlimオルカンは配当再投資の商品。配当金が支払われない代わりに評価額へ上乗せされていきます。では、どのぐらいの配当金がファンド内で再投資されているのか。それを知るには、同じ指数をベンチマークに運用されている姉妹商品、東証ETF『MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信』の分配金利回りが参考になります。
MXSオルカンはそのブランドを見ても分かる通り、Slimオルカンと同じ三菱UFJアセットマネジメントが運用している商品で、こちらは毎年6月と12月の年2回、分配金が支払われます。つまりこの商品の分配金利回りを参照すれば、Slimオルカンでどのぐらい配当金が出ているのかを知ることができます。
【出典】MXS全世界株式(東証)
東証の資料によると、2024年9月30日時点でのMXSオルカンの分配金利回りは1.43%。つまり3,800万円分のSlimオルカンを保有していると年54万円ほどの配当金が再投資に充てられていることになりますから、キャピタルゲインがなくても足が出ている分を多少はカバーできるわけです。
ぼくは基本的には、不足した生活費分だけを適宜オルカンから取り崩していくことを考えています。もちろん場合によってはBTCをうすーく取り崩していくこともあっていいかもしれませんが、税制が変わるまではガチホでいいかなと。
FIRE後の生活費については「定額で」とか「定率で」とか、ここは色々な考え方があると思いますが、そこまでかっちり決めて生活する必要ありますかね、というのが個人的な見解。だって、生きていれば何があるかわからないじゃないですか。
支出なんか減ることもあれば増えることもある。どんなに緻密に計算したって、現実は想像を超えていきます。世界的なパンデミックがあるとか、トランプさんが二度目の大統領になるとか、自分が会社員辞めてるとか、YouTuberになってるとか。B/Sをつけ始めた2018年1月の時点ではどれも想像だにしていなかったわけです。
なのであれこれシミュレーションしてもそこに答えはない、というのがぺいぱのスタンス。もちろん意味がないと言っているわけじゃありません。それも指標の1つにはいいでしょう。でも、自分はこれまで経験に基づく直感で生きてきてるんで、今後もそれは変わらないですね。人はイメージしたところにしか辿りつかないですから。緻密な分析よりも、こういう生活をしていきたい!という思いを大事にしていただく方を、ぼくは皆さんに勧めたいです。
おしらせ
キャラクター”ぺいぱ”がデザインされた「資産運用学園やわらか中学校」公式アイテムがついに販売開始!トイレットペーパーを模したキャラデザの由来は、古くなったお札が再利用されてトイレットペーパーになることや、ウン(運)がつく縁起ものだからなど、諸説あり。いずれのアイテムも日常使いできるシンプルデザインです!ぜひお買い求めください!

さいごに
今回は「FIREするのにいくら必要?」というテーマについて話をしてきましたがいかがだったでしょうか?
なんやかんやと話をしましたが、結論から言えば「必要なのは額よりも型」となりました(笑) ズバリな金額を期待されていた皆さん、すいません。
FIREというのはゴールではなく生活スタイルのひとつでしかありません。自分が目指す生活スタイルを大きく崩してでも達成する必要があるのかと言えば、ぼくはそうは思いませんし、一度試してみて合わなければ、会社員に戻ってもいいわけですし。あまり手段に囚われて目的を見失わないでほしいな、なんて思います。
ぼく、朝に1時間ほど散歩をしているんですよね。オフィス街から公園を回りターミナル駅を抜けて自宅に帰ってくるわけですが、その道中でダンボールを住まいにされている方も見かけるわけです。
こういう方々、概念でいくとFIRE達成者ですよね。だって、生活水準はさておき、収入と支出のバランスを保っているわけですから。1億円だろうが5億円だろうが、それなりの資産を持ってFIREした方でも、満足している人もいれば物足りなさや課題を感じている人もいる。それは路上生活をしている方だって同様なのだと思います。望んでそうなった人もいるでしょうし、そうならざるを得なかった方もいるでしょう。
こうしたことからもわかりますが、FIREに必要な金額は人それぞれだし、そんな基準あってないようなものです。だって生活水準のコントロール次第だから。ぼくはおそらく食費を入れて年間200万円ぐらいの支出であればやれると思います。あえてそれを選んでないだけ。4%ルールでいくと5,000万円になりますね。感覚的にはそれ以下の水準であれば労働収入を得ながらの生活を選ぶでしょう。こうやってなんとなく答えが出せるのは、やはり「自分自身の生活イメージ」と「資産形成の型」があるからです。
重要なのは自分がどんな生活をしていくことを目指すか。そこで何をやりたいのか。そういう具体的なビジョンを持つことこそがFIRE達成に必要な条件な気がします。なお、ぼくは
・人の役に立つ物書きをする(自己実現)
・若手作家の活動支援をする(他社貢献)
この2つを掲げています。何かぺいぱと取り組んでみたいと思われる方、ぜひご連絡をお待ちしています。顔出ししなくて良い案件ならぜひ話をしましょう!
この「やわらか中学校」ではお金や仕事に関する話題を中心に、FIRE生活に突入したぺいぱの日常を赤裸々にお届けしています。ぜひチャンネル登録・いいね・コメントをよろしくお願いいたします!
人生はノーコンティニュー!悔いのないようにやっていきましょう。
では、ごきげんよう。
FIREに必要なのは「生き方のイメージ」と「資産形成の型」