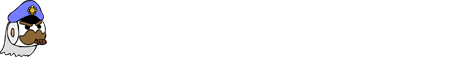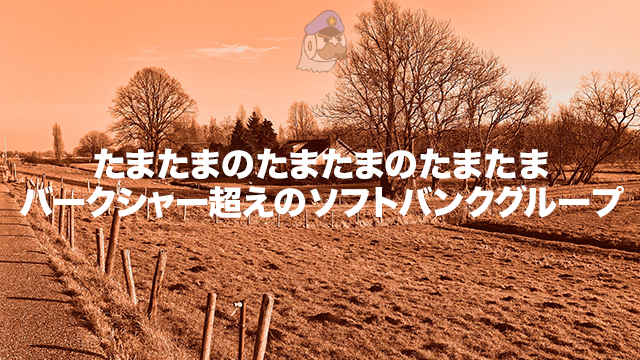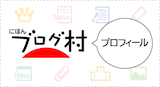・ジェットコースターのような株式市場
・ぺいぱの「頑張らない資産運用」
・長期投資を辞めてしまう主な理由
ごきげんよう、ぺいぱです。
このブログの内容は動画でも解説しています。
上昇も下落も史上初を更新し続け、まさにジェットコースターのような株式市場。もしかすると、せっかく重い腰を上げて始めた株式投資をこのタイミングで辞めてしまったなんて方もいるかもしれません。
株式投資は、手堅いインデックスを選んであとは持ち続けるだけ。それだけで成果が出る。そんなことがよく言われてきました。ではなぜこんな簡単なことを皆ができないのか。その答えがまさに今の相場にあるようにも思うわけです。
ただし、今回のタイミングで市場を離れた人を馬鹿にしてはいけません。人それぞれにお金との向き合い方があるからです。生活に何らかの支障が出ているようなこともあるでしょう。それは、
・株価が気になって何にも集中できない
・不安すぎて夜もぐっすり眠れない
・資産が減ってるので食費も減らす
このようなことです。将来の自分のためにやっていくのが株式投資。こんなことになっては本末転倒ですから、であればすっぱり辞めた方がいい。ぼくはそう思います。
どんなことにも当てはまりますが、長く続けていくためには無理をしないこと。頑張らないこと。ここが重要です。お昼のバラエティ番組「笑っていいとも!」を32年間続けたタモリさんも「頑張ると疲れる。疲れると続かない」と以前のインタビューで答えています。
そう、長く続けたいなら「頑張らない」こと。これが重要だということです。投資に限りません。皆さんもこんな経験良くありませんか?
・筋トレを始めて、当初は毎日ジム通いしていたが、いつの間にか辞めてしまった。
・資格取得を目指して、当初は毎日勉強していたが、いつの間にか辞めてしまった。
・自炊を始めて、当初は毎日作っていたが、いつの間にか辞めてしまった。
ぼくの経験則で言うと、続けることを重視するなら最初からペースを飛ばさない方がいいですね。筋トレだと週に1度程度はジムに行くぐらいにし、気が乗らない時はすっぱりやらない。勉強も気が乗らない時はやらない。このぐらいがちょうどいいわけです。細く長くの精神です。
人って不思議なもので「やろう!」と思い立った時のエネルギーは凄まじい。最初の2週間ぐらいはその勢いが持続します。ただ、そうやってスタートしたものほど失速した後との落差が大きすぎて、もう繋ぎ止めることが難しくなり、結果諦めてしまうんですね。だから続かない。
株式投資に話を戻していくとやはり原理は同じなんだと思います。
・月に10万円積み立てし続けるぞ!
・この商品を一生持ち続けるぞ!
こんな崇高なことを掲げてスタートすると、それが負担になってしまう。ちょっとほころびができると、それがあっという間に広がって、辞めてしまう。だから最初から頑張ってはいけないわけです。では、どう頑張らなければ良いのか? ぺいぱが考える「頑張らない資産運用」というのをシンプルに示すとこうなります。
① 投資していることが日常生活で気にならない。→ OK
↓
NG
①へ
② 投資している金額・商品・購入方法を見直す。↑
「① 投資していることが日常生活で気にならない」のであればOKです。そのまま資産運用を続けていきましょう。もしNGであれば「② 投資している金額・商品・購入方法を見直す」必要があります。見直した上で改めて「①」に戻り、OKになるまで繰り返すわけです。もう、本当にこれだけ。
このサイクルで辿り着いた地点こそが、その人にとって最も適切な「頑張らない資産運用」のポジション。なので、先ほども述べたように、いま株式投資をしていることがシンドイのであればやり方を見直した方がいい。見直すにはある程度の時間が必要ですから、場合によっては一回すべてを辞めた方がいい。そういうことです。
ここまでは非常に定性的な話をしてきました。ここからは具体的に金額・商品・購入方法をどういう基準で自身にあった形にしていくべきか。その手がかりになる話をしていきます。
「投資する金額」の考え方
よく言われるのが「年齢=現金比率」ですね。自分が35歳であれば、保有資産のうち35%を現金、つまり残り65%は運用に回すということです。年齢が上がるほどリスクを減らし、安定した資産(=現金や債券)を多めに持ちましょう、という考え方に基づいています。
ただし、「現金比率=生活防衛資金」というわけでもありませんし、寿命の伸びや定期収入の有無などが考慮されているわけではありません。そのため、ぼくは「目的別にお金を分類」する考え方を採用しています。
A) 生活防衛資金
B) 将来使い道が決まっている資金
C) すぐには使わない予備資金
Aは、その時の生活費(娯楽費を除いたもの)が月に20万円であれば、年間で240万円となります。通常は半年から一年分程度を、何かあった時のために待機させておく。例えば事故や病気で収入が途絶えるなどのケースに備えるわけです。
Bは、家具・家電を買う、旅行に行くなど、近い将来確実に使うことが判明しているお金については分別管理しておくというものです。ではこの「近い将来」というのがどのぐらい先であるべきなのかですが、大体5年以内といったところでしょうか。それよりも先である場合は運用しておいた方が良いと考えられるからです。
Cは、AとB以外のお金です。極端な話、無くなっても生活に支障がないため「無期限である」ということが強みになりますから、こうしたお金は積極的に運用に回したいところです。ぺいぱの場合はこれに当てはめた時の金額がアバウトではありますが300〜500万円となります。
こちらの回「過去7年の現金比率を振り返る」でも紹介していますので、参考にしてください。

「投資する商品」の考え方
では、その資金でどんな金融商品を買うべきか。個人投資家の置かれた状況は千差万別ですから、一言で「はい、これです」なんて答えはありません。ただそれでも、ぺいぱ自身が各年齢の節目で今まったくの一から株式投資をするのであればこれを買うだろうなというものを紹介します。あくまでひとつの参考としてお受け取りください。
20歳 『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』
30歳 『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』
40歳 『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』
50歳 『ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)』
60歳 『ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)』
70歳 『eMAXIS Slim 先進国債券インデックス』
ベースとした考え方はこちらです。
・収入期間が残りどのぐらいか。 ・運用期間が残りどのぐらいか。
「収入期間」というのは仕事で得られる定期労働収入を指します。会社員の方が多いでしょうからここは60歳までと考えます。つまり20歳であれば残り40年間、40歳であれば残り20年間、安定した収入があるとします。
「運用期間」というのは購入した商品をどのぐらい運用できるのかを指します。つまりいつまで生きているのか、ということと同義でもあります。ここは80歳としておきます。かなりざくっとはしていますが、この辺りが商品選定の際の取っ掛かりになっています。
20代のうちは、将来的なリカバリーが効くため、成長性の高い地域に集中投資するのが合理的です。年齢を重ねるにつれてリスク許容度が下がるため、30〜40代では、株式の中でも最大限の地域分散を意識。経済成長が今後どの地域に集中するか予測困難なため広く持っておくという趣旨です。
定年が見えてくる50〜60代では、国内外の株式と債券を半々に配分し、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)に近い安定志向のポートフォリオを意識。値動きが大きいREIT(不動産投資信託)を外すことで、価格変動のブレを抑えることも狙いの一つです。
70代以降は、現金だけで生活するのも選択肢ですが、あえて運用を続けるのであれば、オール債券の投資信託も候補になります。為替リスクを取ってでも利回りを求めたい方は先進国債券、安定性を重視する方は国内債券を選ぶと良い。そんな考え方です。
以前にこちらの回「年代別の投資信託これ1本!:もしもぺいぱが○○歳だったら何を買う?
」でも取り上げていますので、ご興味があればご覧ください。

「投資する際の購入方法」の考え方
ぼくは2021年6月に、それまで保有をしていた米国、中国、東南アジアの個別株を全て売却し、『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』に一本化しました。2,500万円分を一括投資し、その後は2023年12月まで毎月30万円を積み立て購入し続けました。
以前に『オルカン(全世界株式)の「一括投資」vs「一括+積立」vs「積立投資」結局どれが良い?』という回をお届けしたことがありました。

しかし、「どう買うと結果が良いのか」というのは、期間の切り取り方で如何様にもなりますのでここでは改めて語りませんが「生活に支障のない範囲」「無理をしない範囲」での購入になっているかはとても重要です。
通常は、給料(フロー)を得た一部を投資に回す、というのが原資になりますから、自動的に積み立てを選ぶことになるでしょう。あとは積み立て金額をどうするか。3〜5万円前後というのが一般的でしょうか。
その月に、運用へ回しすぎて生活費が足りない。こんなことにならない範囲で決めていく。これが理想ですね。ぼくはかつて生活費が足りなくて、運用中の投資信託を取り崩して食い繋いでいた、なんてことがありました。複利効果も削がれますし手間もかかります。これはできれば避けたいパターンです。
おしらせ
キャラクター”ぺいぱ”がデザインされた「資産運用学園やわらか中学校」公式アイテムがついに販売開始!トイレットペーパーを模したキャラデザの由来は、古くなったお札が再利用されてトイレットペーパーになることや、ウン(運)がつく縁起ものだからなど、諸説あり。いずれのアイテムも日常使いできるシンプルデザインです!ぜひお買い求めください!

長期投資を辞めてしまう主な理由
ここまでは「株式投資に不安を感じたらコレをせよ!」について話をしてきましたが、これはあくまで、ぺいぱがこれまでやってきた考え方を文章化しただけです。ぼくはこうした整理の上で、荒れ狂う株式市場でも日常生活と切り離すことができている。つまりどんなに株式市場が荒れようがそれを気にすることなく生活できているわけですが、すべての個人投資家にパチっとハマるかは分かりません。ただ、頑張らないで資産運用を続けていくための「型」を探る上で、一つのきっかけやヒントにはなるのではないでしょうか。
個人投資家が長期投資を辞めてしまう主な理由を、もう少し噛み砕いて分解していくと、こんなことが言えると思います。
①市場の変動に耐えられない
株式市場は短期的に大きく変動することがあり、初心者ほど急な下落に耐えられずパニック売りをしてしまう。
②思ったよりリターンが出ずに飽きる
期待していたほど早く利益が出ず、時間をかけて複利効果を享受する前に、モチベーションが下がってしまう。
③生活環境や収支の変化
投資を始めたときは順調でも、結婚や子育てなどライフステージが変わることで投資を継続できなくなってしまう。
④投資戦略のブレや間違った判断
投資方針を決めずに始めたり、途中でコロコロ変えたりすると、適切なリターンを得られず諦めてしまう。
⑤投資そのものに興味を失う
長期投資は地味であり、結果が見えにくくモチベーションが続かないことから、お金を他のことに使ってしまう。
今回は「頑張らないことで続けていける」という観点を話の中軸に据えましたが、こうした辞めてしまう理由の理解をすることも効果的かもしれません。
なお、一度「これだ」と思えるやり方を見つけたとしても、それが年齢やライフスタイルの変化とともに変わっていくことは、当然あって良いことです。株式相場が生き物であるのと同じように、個人投資家自身も生き物です。株式投資を続けていくということは、つまり「自分自身との対話を続けていくこと」。そして、その対話の中で資産運用のやり方も、少しずつ変化していって構わない。そう、一度決めたことを頑張って頑なに守り続ける必要はないんです。
今後、ぺいぱも自分の運用に不安を感じる時がくるかもしれません。そうなったら争わず、冷静に今回の話通りのプロセスで再確認をしていきます。
最後の最後にお知らせ! YouTubeで「ぺいぱのひとりごと」というサブチャンネルをやっていまして、原則、平日の朝7時からライブ配信しています。お金や仕事の話題を中心に、直近の出来事でぺいぱが興味のあるものを取り上げ、好き放題喋り倒すラジオみたいな内容です。通勤・通学のお供に最適だと思いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。
人生はノーコンティニュー!悔いのないようにやっていきましょう。
では、ごきげんよう。
続けるには頑張らないこと。