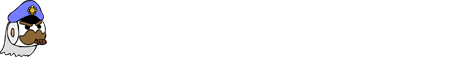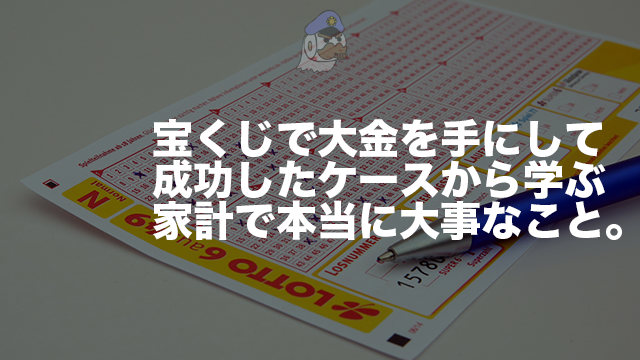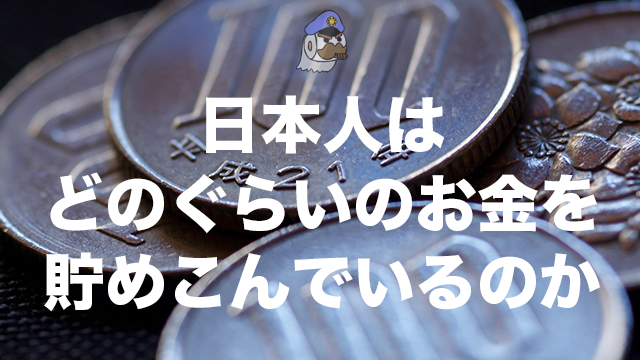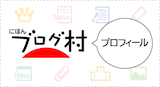・自分の資産運用における考え方
・ほったらかし投資の基本
・親の資産管理について
おはーん、ペーパー先生です。
経済評論家で楽天経済研究所客員研究員の山崎元(やまざき・はじめ)さんが、
資産運用における「ほったらかし投資」に関する
インタビューに答えた記事が掲載されていましたので紹介します。
【出典】資産運用は無理せず放置を 山崎元さん「ほったらかし投資」のすすめ(女性自身)
2022/05/12 15:50
大きく2つのポイントを挙げています。
1つは自分自身の資産運用における考え方。
2つめが親の資産管理について。
順番に見ていきましょう。
自分の資産運用における考え方
投資信託での資産運用にあたり、3つのステップでお話をされています。
■運用するのにあたり
・原則は『長期・分散・低コスト』。
・おすすめは『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』。
・理由は全世界の株式指数と連動する、運用管理費用が安い。
・(株式市場は)短期的には価格が下落することもあるが、長期的に見れば価格は上昇してきた。
・購入手数料が安いネット証券で運用するのがおすすめ。
・証券会社の窓口で購入もできるが、余計な商品を買わされないよう気を付ける。
・iDeCoやつみたてNISAなど、税の優遇が受けられる制度を目いっぱい活用する。
■運用額について
・月の生活費の3~6カ月分を銀行口座に残し、残りを運用資金というのが基本。
・投資信託は『リスク資産』。最大4割ほど増える可能性の一方、3分の1が減るリスクもある。
・資産が100万円減ることまでは許容できるなら、投資額は300万円になる。こんな考え方。
・残りは「無リスク資産」として、個人向け国債か、1行1,000万円の範囲で普通預金のまま保有。
■運用開始後は
・あとは『ほったらかし』。大げさに言えば、投資したことも忘れているくらいでいい。
親の資産管理について
また、山崎さんからのアドバイスとして、自分の資産だけではなく、
親の資産についても守る工夫が必要だと話されています。
「親が認知症になって口座が凍結されたり、変な保険や投資信託を買わされてしまう例も多い。そうした場合に備えて、『財産管理等委任契約』や、あらかじめ家族を後見人に指名する『任意後見契約』を活用して、親のお金を管理できるようにしておくといいですね。」
自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するもの。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づく。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができる。
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めておく制度で、公正証書を作成する。
つまり、今は元気だけれども、今後に不安がある。
今のうちに資産の管理を任せられる人を指定しておく。
そんな制度です。
■「公正証書の作成有無」
→財産管理等委任契約:無し
→任意後見契約:有り
■「委任された人に対するチェック機能の有無」
→財産管理等委任契約:無し
→任意後見契約:有り(※任意後見監督人の選任)
■「手続きの迅速性」
→財産管理等委任契約:早い
→任意後見契約:手間がかかる
このあたりはぼく自身も、両親が70歳を超えましたので、
考えておかなければいけない分野です。
さいごに
今日は山崎元さんのインタビュー記事をもとに、
資産に関して抑えておきたいポイントを、
「自分の資産運用における考え方」
「親の資産管理について」
それぞれについて触れてきました。
資産形成を捉える際、自分自身だけのこととして考えがちですが、
こうした話題は家族全体で話し合いをしていくことも大事。
そんなことを、改めて強く実感しました。
では、ごきげんよう。
よろしければこちらの記事もご覧ください。



自身の資産運用がしっかり回り始めたら、次は家族に視野を広げよう。