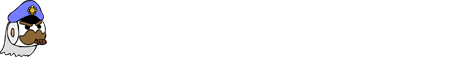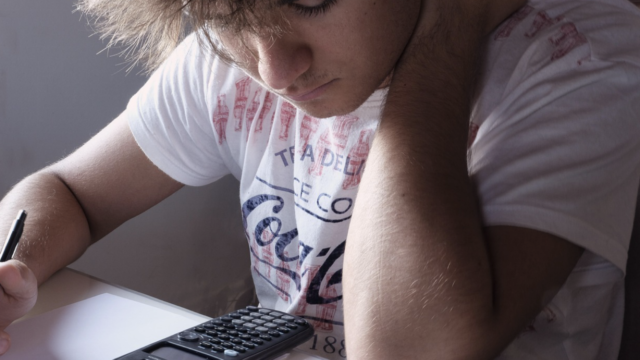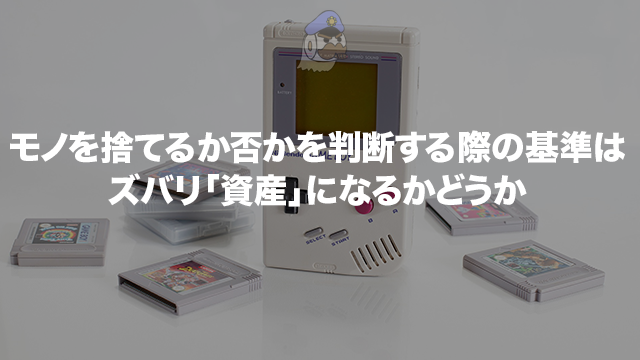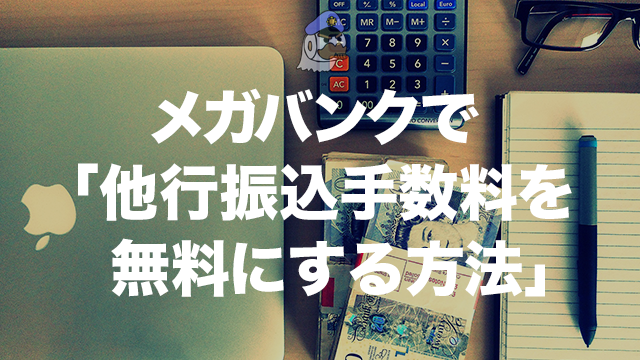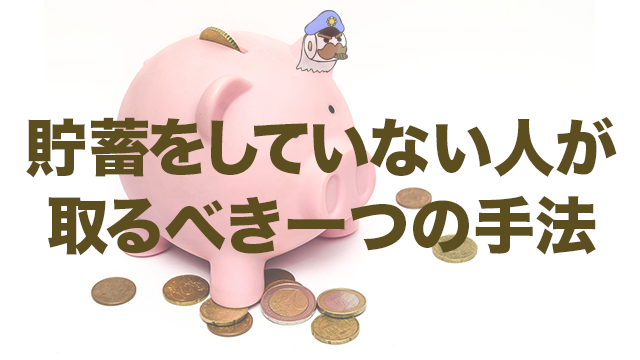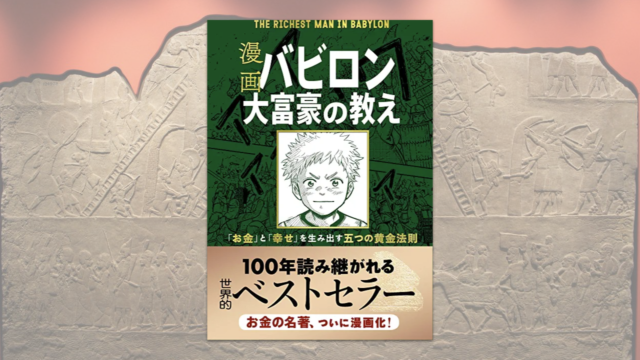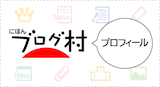・インフレが家計に与える影響
・現金100%のリスクとは
・インフレに強い資産をどう持つか
ごきげんよう、ぺいぱです。
このブログの内容は動画でも解説しています。
「また値上げか…」というため息が、もはや毎月のように聞こえてきます。実際、2025年7月の飲食料品の値上げは2,105品目。前年同月の5倍以上に跳ね上がりました。しかも、値上げ率は平均15%と、家計へのインパクトも相当なものです。
調味料やお菓子、パスタソースに米飯(べいはん)製品、果てはビールや清涼飲料まで。内容量を減らして価格を据え置く実質値上げも含めると、私たちが日常的に手に取る食品の多くが静かにそして力強く高くなり続けていることがわかります。
しかもこれは一時的な話ではありません。2025年通年での値上げ品目は、すでに1万8,000品目を超え、年間2万品目に達する勢い。背景には、原材料高だけでなく、光熱費や人件費、物流費の高騰など、複数のコスト上昇が同時に進んでいる構造的な要因があります。
思えばぺいぱが幼少期に夢中になっていた「ビックリマンチョコ」。
もうかれこれ40年近く前なわけですが、そんな当時は1つ30円。じゃあそれがいまいくらかといえば100円。なんと3倍以上になっています。ま、これにはシールがおまけとして付いている以上、商品価格に対して景品の価値が高すぎてはいけないと定めた景品表示法の影響もあるとかないとかで、シールの質を維持するためには価格を上げざるを得なかったという事情もあったようですが。
ほかにも みんな大好き「うまい棒」。1979年から2022年まで、約43年間にわたり価格は10円で据え置きとなっていました。それが2022年に12円へ値上げ。そして2024年10月からは希望小売価格が12円から15円へ再値上げされました。
こうやってお菓子の値段を見ていくと、「ああ、世の中のモノやサービスって値段が上がってるなぁ」としみじみ実感するわけです。
そんなわけで日本はいま「インフレ」真っ只中にあります。インフレーションとは、物価が継続的に上昇する経済現象のことです。物価が上がっているというのは、裏を返すと「お金の価値が下がっている」ということでもあります。
だって令和のいまは100円あってもうまい棒は10個買えないし、ビックリマンチョコに至っては1つしか買えないわけですから。つまり「同じお金なのにできることが減っていく」というのがインフレの怖さです。
主要な中央銀行、たとえば日本の日銀、アメリカのFRB、ヨーロッパのECBなどは、「年率2%前後の物価上昇こそが、健全な経済成長に必要だ」と考えて政策を動かしています。つまり、上振れたり下振れたりするけども、最終的にはそこを目指して設計されている社会。現金だけを抱えておくと、理論上は毎年2%ずつジリジリと貧しくなる。そんなルールの中に、私たちは生きているわけです。
さて、リスク資産にお金を投じる資産運用。新NISA制度のスタートや、高校での金融教育開始などもあり、より身近になってきた感じもありますが、それでもまだまだやっている人は一握りです。でも元本割れするリスクをとってまで、なぜ我々は資産運用をする必要があるのか。その理由がまさにインフレ社会にあります。
今回は、このインフレを入り口に、資産運用の必要性を深掘りしていきたいと思います。「投資とか難しそう…」「今さらやっても遅い?」と思っている方も、これを見終わる頃には、きっと一歩踏み出したくなるはずです。
ぜひ、最後までお付き合いください!
インフレ2%の破壊力
冒頭で「年2%くらいのインフレ」について触れました。実際には日本の物価上昇はそれをかなり上回っているわけですが、2%でもこれが10年、20年、30年……と積み重なったらと考えるとなかなか怖い。
年2%ずつ物価が上がっていくと、概算で35年すると購買力はほぼ半分になります。つまり、100万円でいま買えているものが、35年後には200万円ないと買えなくなっている、そんなイメージ。これは「1.02の35乗 ≒ 2.0」という計算から導き出せます。
つまり、もしもあなたが「老後に備えて貯金のままで何十年と寝かせていたら」、気づいたときには実質的にお金の価値が半分になっているかもしれない。これは冗談でも脅しでもなく、想定しておくべき普通の未来なんです。
預金だけはむしろリスク
最近は、長らく続いた金融緩和も一段落し、銀行の預金金利がわずかに上昇してきました。とはいえ、その金利はせいぜい年0.2%前後。一方で、先程の物価。2020年平均を100とした指数で見ると、2025年3月には110を超えており、つまりはこの5年間で物価は約10%上昇したことになります。比較するとこう。
消費者物価指数:
2020年:100
2025年:110(+10%)
銀行預金:
2020年:100万円
2025年:約101万円(+1%)
およそ5年間でモノの値段は10%上がったのに、預金はたったの1%しか増えていない。つまり、銀行に預けていればお金自体は減ることがありませんが、その価値は大幅に目減りしたことになります。
かつての日本のように、物価下落が続く「デフレ」の時代であれば、お金をコツコツためるのが「堅実で正しい」と言えました。でも、今はもう違うルールの社会が動き始めています。
インフレに対抗するには
では、そんな物価が上がる時代、現金の価値が下がっていく状況に、どう対抗すればよいのか。答えはシンプルです。インフレに強い資産を持つこと。物価が上がる=モノやサービスの価格が上がるということですから。その恩恵を受ける資産をお金から変えて保有しておく。わかりやすいものを挙げると具体的にはこの3つ。
① 株式(国内・海外)
企業は原材料や人件費が上がれば、製品価格に値上げという形で転嫁します。つまり、インフレとともに売上や利益も増える構造。それが株価に反映されていきます。
② 外貨資産(米ドルなど)
円安が進めば、外貨建ての資産は円換算で増える。特に日本のようにインフレと円安が同時進行する局面では、外貨は強い味方になります。
③ コモディティ(原油・金ETFなど)
資源そのものの価格上昇は、インフレの主因(しゅいん)でもあります。金や原油などは、インフレ時の保険として、少量でも持つ価値があると言えます。
もちろん、全部を買い集める必要はありません。インフレ負けしない資産を少しずつポートフォリオに混ぜていく。「現金100%」から「現金+リスク資産」に変えるだけで、対抗力は格段に上がります。
そして、それを実行するうえで大切なのがこちら。
⏰ 長期:
短期的な値動きに一喜一憂しない。
15年以上の時間軸で構えることで、
リスクは平均化されていきます。
🌏 分散:
国・資産クラス・通貨などをバラすことで、
特定のリスクに偏らない。
世界中にまんべんなく乗ることが鍵です。
💰 低コスト:
各種手数料や信託報酬など、
コストは確実なマイナスとなります。
ここだけは、自分でコントロール可能な部分です。
地味でいい。コツコツでいい。派手に一発当てるより、負けにくい仕組みを持つことの方がこの不確実な世の中を渡り歩くのによっぽど堅実なんですね。
なお、ぺいぱは現金のほかにオルカン(全世界株式)と暗号資産(ビットコイン)を保有することで、インフレに抗おうとしています。

お金から何に替えるか
ぺいぱは現在40代。この「やわらか中学校」をご覧いただいている方もこの前後の方が多いと思います。ですが、これは40代だけの話ではありません。若い世代にとっては、長く付き合っていく現実ですし、上の世代にとっても「長生きするリスク」を見据える必要があります。
インフレは黙っていても進みます。そしてそのたびに、あなたの財布からこっそりと、しかし確実に「購買力」を奪っていく。でも仕組みを知り、「長期・分散・低コスト」の原則を淡々と回していけば、インフレという波にも流されずに漕ぎ進むことができます。
もちろん資産運用はインフレのためだけに必要というわけでもありません。自分の稼ぎだけで補えないお金を育てていく。それはつまり「老後資金」「教育資金」「住宅資金」。そして突然の事故・病気などの備えも必要だからです。
年齢や家族構成、住まいの地域などのステータスはさまざま。人の数だけ資産運用のあり方は存在するといっても過言ではありません。自分が置かれた状況で、何が最も合理的な備えになるのか。トライアンドエラーで正解を導いていく。だからこそ早い時期からの資産運用が良いとされるわけです。
ぼくは株式投資こそかなり以前からやっていましたが、資産形成(お金を計画的に育てる)の考え方で行動するようになったのは40歳になってから。「後悔先に立たず」で、あのときああしていれば…なんてことは通用しません。遅く始めるほどハンデはあるわけですが、それでもいま時点が一番最速であるとも捉えられます。そんな思いでやっとこさ何とか形になってきたわけです。
なお、物価上昇の事例でお伝えしたビックリマン。このシール集めがぺいぱ少年の楽しみだったわけですが、一番好きなキャラクターは悪魔vs天使シリーズ第7弾ヘッドの聖ボット・ヘラクライスト。聖親12天使の力で完全体となり、ブラックゼウスを退治した際の赤シール姿です。このシール、現在の買取価格は状態にもよりますが5万円前後。そう、お金を資産性のあるモノに替えておくことの重要性がここからもわかります(笑)
みなさんは、インフレ時代のお金の守り方、どう考えていますか? 金融商品に限らず、腕時計とかワインとかウイスキーとかスニーカーとかレトロゲームとか。需要しっかりあって供給が足りていないものを手にしていく打ち手はいろいろありますが、ぜひコメント欄で教えてください!
おしらせ
キャラクター”ぺいぱ”がデザインされた「資産運用学園やわらか中学校」公式アイテムがついに販売開始!トイレットペーパーを模したキャラデザの由来は、古くなったお札が再利用されてトイレットペーパーになることや、ウン(運)がつく縁起ものだからなど、諸説あり。いずれのアイテムも日常使いできるシンプルデザインです!ぜひお買い求めください!

さいごに
この「やわらか中学校」では、取り上げてほしいテーマを募集しています。すべてにお答えできるわけではありませんが、今後のテーマ選びの参考にさせていただきます。また、ぺいぱに聞いてみたいことなども大歓迎です! ぜひコメント欄で教えてください!
人生はノーコンティニュー! 悔いのないようにやっていきましょう。 では、ごきげんよう。
お金にも働いてもらい、インフレに対抗していこう!