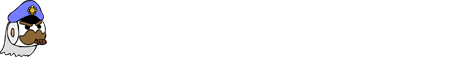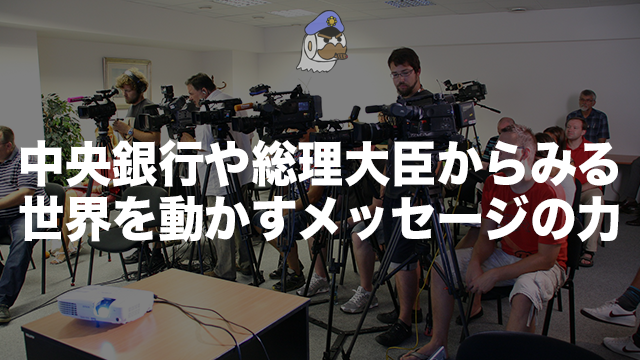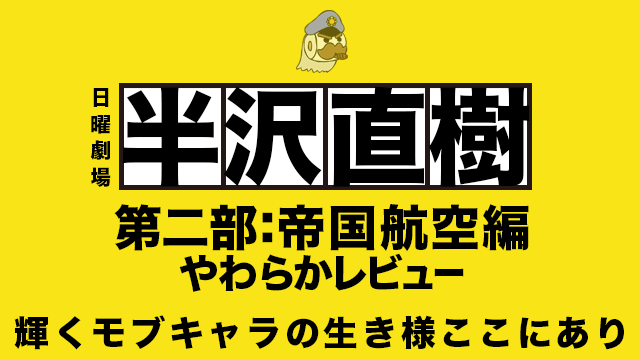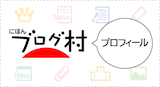・人生時計の考え方とその計算方法
・自分の現在地を知り今後の生き方を見直す
・ライフステージに合わせた行動や意識
ごきげんよう、ぺいぱです。
このブログの内容は動画でも解説しています。
人生をどのように捉えるかは人それぞれです。長いと感じる人もいれば、あっという間だと感じる人もいるでしょう。資産形成をしていると「時間をいかに活かすか」という問いに直面することが多くなります。投資や副業など、時間を味方につけてこそ成果が出るものがあるからです。同時に、「いま自分は人生のどのあたりを歩いているのだろう」とふと考えてみたくなることもありますよね。
そんなときに役立つのが「人生時計」という考え方。たとえば「45歳=15時(午後3時)」といった具合に、年齢を3で割り、1日24時間のうちどこに位置しているかを見立てるというアイデアです。人生を24時間に例えることで、
「こんなに時間が過ぎてしまった」
「でもまだこんなに残っている」
と、残り時間を客観的に捉えられるのがポイント。
今回は、この「人生時計」を使って自分の居場所を把握するメリットや、ライフステージごとに意識しておきたいことなどをまとめてみたいと思います。今後の生き方や資産形成の戦略を考える上で「いま何時か」をはっきりさせることは思いのほか有用かもしれません。
「人生時計」と聞くと、「何だか重い話」「寿命を意識するのはちょっと…」と敬遠したくなる方もいるかもしれませんが、心配ご無用。あくまで”客観的な目安”として気軽に捉えてください。もしこの考え方がしっくり来なければ、途中でやめていただいても結構です。ただ、現時点が
・朝なのか
・もう昼下がりを過ぎているのか
・夜に近づいているのか
を視覚的に理解するだけでも、行動を変えるきっかけになります。
資産形成の文脈でよく語られる「若いうちから始めれば複利効果が大きい」「定年前までに余裕資金を作っておきたい」といった話も、実は人生時計と深く関連しています。20代であれば午前中の体力がみなぎる時間、40代〜50代なら午後に差し掛かる時間、60代なら夜に近い時間…と捉えれば、「自分はいまどんな行動を優先すべきか?」が明確になるからです。
それでは、ここからは「人生時計」の具体的な仕組みと、その活用の仕方を解説していきます。最後には、これからの人生設計を考える上でのヒントもまとめますので、ぜひ最後までお付き合いください。
1時:03歳
2時:06歳
3時:09歳
4時:12歳
5時:15歳
6時:18歳
7時:21歳
8時:24歳
9時:27歳
10時:30歳
11時:33歳
12時:36歳
13時:39歳
14時:42歳
15時:45歳
16時:48歳
17時:51歳
18時:54歳
19時:57歳
20時:60歳
21時:63歳
22時:66歳
23時:69歳
24時:72歳
人生時計とは?
まずは人生時計の基本的な考え方を整理しておきましょう。計算方法はとてもシンプルで、自分の年齢を3で割り、その結果の数字を24時間制の時刻に当てはめるというものです。たとえば45歳なら「45÷3=15」、つまり一日のうちの15時(午後3時)というわけですね。
<「45歳=15時」のイメージ>
一日が24時間あるのと同じように、仮に人生を72年(24×3)とざっくり設定すれば、45歳は「人生のちょうど3/4に差し掛かる手前」ということになります。15時と考えると、朝から8時間以上過ぎているので結構な時間が経っていますが、夜まではまだ少しある、という印象も同時にあります。
… …
<何歳までを想定するか>
一般的には72年(24×3)を想定するのが分かりやすいですが、平均寿命や自分の健康状態を踏まえて「80年」「90年」で組み立てる人もいるでしょう。その場合は、「24時間=80(90)年」で計算するとよいかもしれません。
… …
<朝・昼・夕方・夜という区分>
ざっくりと「朝」は0〜25歳、「昼」は25〜50歳、「夕方」は50〜75歳、「夜」は75歳以降…と考えてみるだけでも、自分がいまどのあたりにいるかをイメージしやすくなります。
この計算自体はとても単純ですが、その数字を視覚化することで「自分はいま◯◯時なんだな」と客観的にとらえ、残り時間に対する意識が高まるというメリットがあります。
人生時計を使うメリット
人生時計最大の利点は、”客観性”を与えてくれる点にあると言えます。人は年齢を重ねると「もうこんなに歳を取った」「まだまだ若いから大丈夫」など、自分に都合の良い解釈をしがち。でも人生時計で「◯時」という具体的な数字に当てはめると、その曖昧さを払拭し、今どの段階なのかをかなり冷静に見られます。
<「午前中」なのか「もう夕方」なのか>
たとえば30歳前半であればおよそ10時前後、まだ朝の名残がある時間帯かもしれません。ここから昼まではまだ時間がある、と感じるかもしれませんし、「もう10時? 朝寝坊しちゃったな」と焦る気持ちになる人もいるでしょう。どちらにせよ、実感が湧きやすくなります。
… …
<残り時間から逆算できる>
人生時計で見ると「あと数時間(=十数年)しかない」ということが一目で分かる場合があります。たとえば60歳くらいだと「20時(夜8時)」あたり。それまでにやりたいことがまだたくさんあるのか、またはゆっくり過ごしたいのか。時間の大切さを痛感する機会になるでしょう。
… …
<行動を起こす原動力になる>
「まだ朝だから大丈夫」と何もしないか、「あと数時間しかないから急がなきゃ」と積極的に動くかは、自分次第です。何にせよ、具体的な残り時間を数字で捉えると、行動を起こすきっかけになりやすいのは確かです。
人生時計の考え方は、心理的にややシビアに感じる部分もあるかもしれませんが、それゆえに行動力を高めるスイッチとなり得ます。
時間帯別のイメージ
ここでは人生時計を24時間=72年と想定し、ざっくりとした時間帯ごとにやるべきこと・意識することを考えてみましょう。もちろん個人差はありますが、一つの目安として捉えてみてください。
<🌅 朝(0〜27歳):0時〜9時ごろ>
・学びと経験の時間:
基礎体力や基礎学力を身につける時期。将来を見据えた土台づくりが重要。
・親や周囲の影響が大きい:
家庭環境や教育が大きく人生に左右するが、自分でも多種多様な体験を試しておきたい。
… …
<☀️ 昼(27〜48歳):9時〜16時ごろ>
・キャリアの本格化:
社会人としてのキャリアを積み上げる時期で、仕事やスキルアップに集中しがち。
・資産形成の大チャンス:
複利効果を活かすならこのあたりがベスト。投資や貯金の土台を整えることで後がラクに。
… …
<🌆 夕方(48〜57歳):16時〜19時ごろ>
・セカンドキャリアやリタイア準備:
定年を迎えるかどうか、あるいは早期リタイアを目指すかなど、次の段階への移行が近い。
・健康管理が欠かせない:
体力の衰えや病気リスクが高まるため、健康を維持する習慣が重要。
・家族との向き合い方:
子育てが終わる一方で、親の介護や自分自身の老後を考える時期にもなる。
… …
<🌃 夜(57歳〜):24時以降>
・人生の総仕上げ:
ここまで何を積み上げてきたか。趣味を極めるか、静かに余生を楽しむか、考え方次第でやれることは多い。
・社会とのつながり:
仕事をリタイアしていてもコミュニティとの交流やボランティアなど社会参加を続けることで充実感を得られる。
こうして見ると、「いま何時ごろだろう?」と当てはめるだけで、自分のライフステージに合わせた行動指針が見えてくるかもしれません。
人生時計を使ったセルフチェック例
<短期ゴール(数年スパン)の設定>
「あと4時間で夜になる」とイメージしたら、それはおよそ12年くらい先(≒4×3)です。12年後に何を実現したいか、そこから逆算して今どんな準備をすべきかを考えるのに役立ちます。
… …
<やりたいことリストと照らし合わせる>
旅行、資格取得、起業、資産形成の目標額…いま何時かを知ることで「これはそろそろやっておかないと、夜になるまでに間に合わない」という気づきが得られます。
… …
<人間関係や家族関係を再チェック>
同世代の友人や子どもの年齢を、人生時計の観点で見てみると、「子どもはまだ朝なのに、自分は午後」というようなギャップを感じるかもしれません。その理解が相互のコミュニケーションにプラスになる場合があります。
… …
<資産形成プランの再構築>
20代なら午前中、30代〜40代なら昼過ぎ、50代〜60代なら夕方、と捉えると、「いま複利効果を最大化すべきか」「リスク資産を少しずつ減らすか」といった運用ポートフォリオの考え方に生かせます。
人生時計と資産形成の関係
資産形成には「若いほど有利」という定説がありますが、それは時間を味方につけられるからです。もし自分が20代なら人生時計で言うと「7時」前後かもしれません。「これから一日の大半(人生の大半)が残っている」と考えられるメリットを最大限に活かし、リスクを取った投資や自己投資を行うのもアリでしょう。
一方、40代や50代であれば午後に差し掛かっているイメージ。「もう半日以上が経っている」「夕方になる前にやれることをやっておこう」と考えることで、限られた時間をより大切に使うきっかけになるはずです。無理にハイリスク投資を行うより、安定した資産保全を重視するのか、または後半にもうひと花咲かせるべく新たなチャレンジをするのか、選択肢はいろいろありますが、どちらにせよ「いま何時か」を把握する意義は大きいでしょう。
人生時計の注意点
<人によって長さが違う>
平均寿命は伸びており、72年を超えて80年、90年生きる時代になっています。むしろ「人生100年」と言われることも多いです。なので、あくまで72年設定は一つの目安として捉え、状況に応じて修正が必要です。もちろん72歳以降は延長線だと捉えても良いでしょう。
… …
<急な体調変化・アクシデントは計算外>
いつ事故や病気になるかは誰にも分かりません。人生時計が示す残り時間は保証されたものではなく「もし何事もなければ」という仮定の数字にすぎないと心得ましょう。
… …
<年齢だけで人生を区切るのは乱暴>
年齢は重要な指標ですが、人によってキャリアのスタート時期や家庭環境など大きく異なります。人生時計は便宜的な目安であり、一律に「40歳だから12時」というように考えて他人と比較するのは本質からズレてしまいます。
… …
<焦りすぎは逆効果>
時間が少ないと感じて極端な行動に出るのは危険です。特に投資や事業で無理をして失敗すると、せっかく残っている時間を余計なストレスで浪費しかねません。「残り時間を充実させるためのヒント」として柔軟に活かすのがよいでしょう。
人生時計を実践に活かすコツ
<実際に時計を描いてみる>
アナログ時計の文字盤に年齢を当てはめ、「いま◯時ごろ」を書き込むと、視覚的なインパクトが大きくなります。さらに夜までの残り時間(=十数年、数十年)を筆記してみると「何をやるべきか」が見えてくるかもしれません。
… …
<家族やパートナーと話し合う>
それぞれの人生時計を共有すると、「お互い、いまこんな時間帯だよね」という共通認識が生まれやすいです。夫婦間で目標を設定したり、子どもの年齢と照らし合わせて教育方針を考えるのも有効です。
… …
<定期的に見直す>
年齢の進行だけでなく、人生のイベント(転職、結婚、出産、早期退職など)によって計画は変わります。人生時計も、1年に一度ぐらいは自分の位置を確認して思考を更新すると良いでしょう。
… …
<楽しむ感覚を忘れない>
人生時計は「時間が減る恐怖」を煽るものではありません。あくまで「自分の貴重な時間を大切にするためのツール」として扱い、「あと◯時間で何を楽しもうか」「昼のうちにこんなことをやろう」とポジティブに考えるのがポイントです。
さいごに
今回は「人生時計で残された時間を可視化しよう」というテーマで、人生を24時間に例えて年齢を3で割る考え方をご紹介しました。朝なら朝なりの、昼なら昼なりの、夕方や夜ならそれぞれのタイミングなりの行動があるものです。
1時:03歳
2時:06歳
3時:09歳
4時:12歳
5時:15歳
6時:18歳
7時:21歳
8時:24歳
9時:27歳
10時:30歳
11時:33歳
12時:36歳
13時:39歳
14時:42歳
15時:45歳
16時:48歳
17時:51歳
18時:54歳
19時:57歳
20時:60歳
21時:63歳
22時:66歳
23時:69歳
24時:72歳
資産形成という面だけ見ても、若いほど複利を活かせる、時間を味方にできるというメリットがあり、一方で年齢が上がれば「守りの資産運用」や「引退後の生活費」を考える時期が訪れます。人生時計を使って客観的に「◯時だな」と理解しておくと、今どの程度リスクを取れるのか、あるいは安全志向にシフトすべきなのかを考えやすくなるかもしれません。
また、「いま午後3時くらいだ」と思えば、そこから夜(=老後)までの残り時間はあと数時間、つまり数十年ほど。多いと見るか少ないと見るかはその人次第ですが、
「もっと余裕があると思っていたが、意外と少ないかもしれない」
「限られた時間をどうやって有効活用しよう」
と、良い刺激を受けるケースもあるでしょう。
もちろん、人生時計はあくまで一つのフレームワーク。人によって歩むペースは違いますし、寿命も伸びたり縮んだりします。しかし、この考え方を取り入れるだけで、日々の予定や行動の優先度がすこしクリアになることも多いわけです。日常生活の中で「昼過ぎにやっておきたいこと」「夕方までに片づけたいこと」をイメージするように、人生のタスクや目標を配置すると、思わぬやりがいやモチベーションにつながるものです。
人生はノーコンティニュー! 悔いのないようにやっていきましょう。
では、ごきげんよう。
自分の現在地を知る。それが気付きになる。