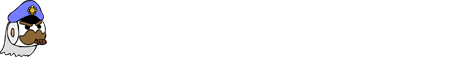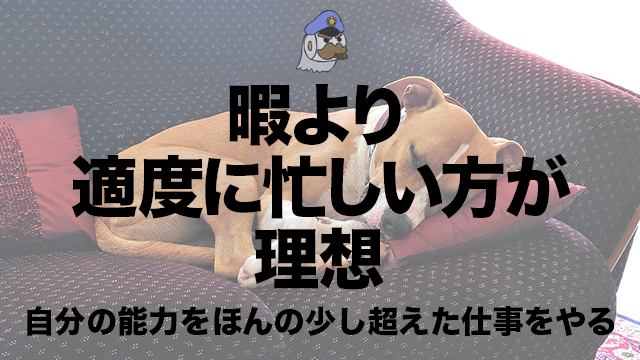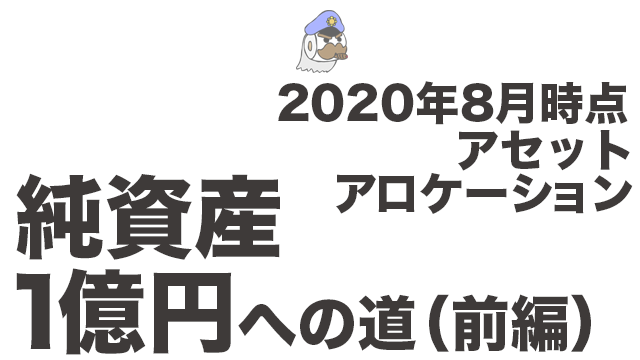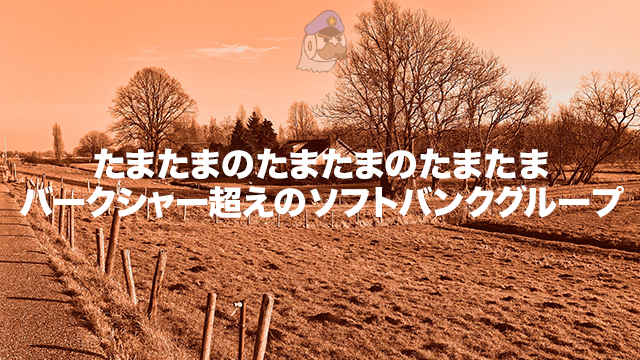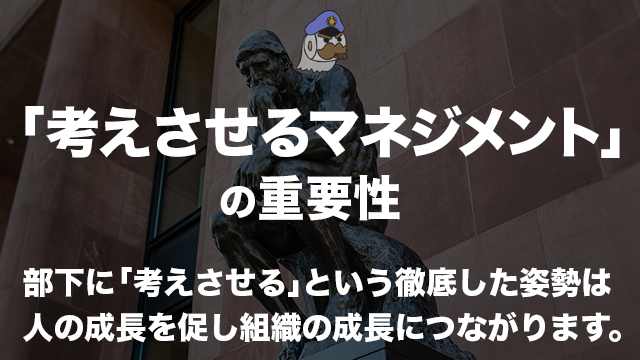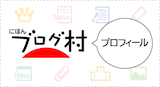・ぺいぱの純資産推移
・資産形成における称号
・富を築いていくための土台
ごきげんよう、ぺいぱです。
このブログの内容は動画でも解説しています。
ぼくが純資産ベースで億り人に到達したのは2024年末でした。たまたまではありますが、四半世紀続けてきた会社員を卒業したタイミングと同じなんですね。

手元の表計算ファイルで最古の統計が残る2017年末から見た純資産推移はこんな感じになっています。この間、保有している商品の中身こそ変わっていますが中核を占めるアセットクラスは株式・暗号資産・不動産・現金で、現在に至るまで大きく変わっていません。
2017年末:2,002万円
2018年末:2,026万円
2019年末:2,649万円
2020年末:3,829万円
2021年末:4,919万円
2022年末:5,517万円
2023年末:7,314万円
2024年末:1億183万円
※数字は四捨五入
2020年以降の数字上昇が大きくなっていることがお分かりいただけると思いますが、まさにここが、意識と覚悟を持って資産形成に臨んだ転換点だったわけです。早期退職後の2025年は、各種税金支払いが重くのしかかるため支出が超先行していますが、運良く株式市場は堅調でしたので、いまのところ資産は大きな増減なく過ごすことができています。
さて、1億円という額ですが、それ以前の数千万円から桁が変わるということに加え、「億万長者」「億り人」「ミリオネア」といったような単語も存在するなど、資産形成をしているすべての人にとってある種の称号のようなものです。
この金額が何かを保証してくれるわけでもありませんし、達成することで人生が大きく変わることもありませんが、でもなぜか目指したくなる。そんな不思議な魅力がある値です。宝くじとか相続などではなく、自分自身の力でこれを達成するためには、
・とにかく稼ぐ
・できるだけ節約する
・余剰資金を徹底的に運用へ回す
このサイクルをやり続ける必要があり、これはある意味で修行の道です。ですので、先ほどは億り人が称号のようなものだと言いましたが、資産形成界における免許皆伝、アバンの印、界王様の道着。そんな位置付けとも言い表すことができるでしょう。
そして修行の道には色々な罠が仕掛けられています。億り人が遠のいてしまう罠です。富士山の登頂は山梨側と静岡側のルートがあるように、億り人への道も人の数ほどそのルートがあります。つまり歩んでいく道のりによって罠のポイントも変わってきます。
今回はあくまでぺいぱが歩んできた億り人への道で「これは罠だな」と実際に感じたものを取り上げていきます。万人に当てはまる内容ではありませんが、現在資産形成をされている方々には何らかのヒントや気付きになるような内容をまとめていきますので、ぜひ最後までお楽しみください!
億り人を遠ざける5つの罠
では、さっそく見ていきましょう!
自分の力だけで億り人到達を目指す場合、最重要となるのは社会人での稼ぎです。いくら節約を頑張っても限度がありますし、運用でお金を育てるにしてもそのための種銭が必要だからです。そこへの近道は、誰もが知る有名大企業への勤務で出世して稼ぐことだと思われがちですが、実際どうでしょうか。
ぼくは社員数名のベンチャー企業で社会人の第一歩を踏み出し、その後に転職して上場しているIT系大手2社で勤務を続けてきました。
当初はデザイナーでスタートをし、最終的には管理職でキャリアを終えたわけですが、最終年収はおよそ1,400万円。飛び抜けて高年収だったわけではありませんが、世の中の平均年収を踏まえればかなり上振れた稼ぎを得たことになります。
いま振り返ると、ポイントとなったのは大企業へ飛び込む前に、ベンチャー企業に在籍していたこと。デザイナーだったとはいえ小さな会社です。グラフィックデザインだけやるなんて環境はなく、Webサイトからパンフレット、イベント企画や企業取材、雑誌原稿執筆、お茶汲み、掃除に至るまで、職業を規定するのが難しいぐらいの幅で仕事をしていました。自ら望んでというよりは、有無を言わさずそういう環境だったということです。
当時はそれが良い悪いなど考える余裕すらなく、ただがむしゃらに突き進んでいましたが、今振り返ればここでの経験が「どんなことでも臨機応変に対応していく耐性」を身につけるきっかけになったわけです。これがあったからこそ、その後の転職で稼ぎを高めることができたと考えています。
20代・30代・40代と社会人を駆け抜けてきましたが、明らかに20代は吸収する力や壁を乗り越える力が高いし、そこで得た知識や経験をその後の人生で長く活かせます。まさに今YouTubeやブログ運営で、ネタを考える、スライドを作る、原稿を組み立てる、四コマ漫画を描いていく。このようなあらゆることに活きています。
会社員は構造上、「業界×職種」による組み合わせで考えることができます。
<業界について>
できるだけ成長しているところを選んだほうが良い。給料のベースアップが狙いやすいから。
<職種について>
自分が興味関心のある分野を選んだほうが良い。多少嫌なことがあっても続けられるから。
会社勤務に限りませんが、仕事を長く続けていくということは、お金における複利効果と同じように、そこで得たことを通じて将来的に色々な可能性やチャンスが増えていくことになります。
ぺいぱは、ベンチャーから大企業まで経験をしてきたので実感があるのですが、新卒で直接大企業入社する場合はどうしても担当範囲が限定的になりがちです。もちろん10年、20年と勤務を続けていれば、動かせる予算はベンチャーとは比べ物にならないほど膨大なものになるかもしれません。
ただ、人の成長スピードは加齢とともに鈍化しますから、若いうちにどれだけたくさんの打席に立って自分自身の可能性を広げられるのかを重視した方が結果的に稼ぐ力に結びつく。ぼくはそう考えています。
だからこそ、会社員の立場を無くしたときに、自身の能力が世の中で通用するかどうかを節目節目で考えてみると良いと思います。その会社の中でしか活かせない知識や経験ばかりを積み上げているなんてことは良くあるからです。
すでに高齢である場合など、置かれている状況によっては現在の延長線上でそのまま生活をしていく方がいい場合もあるでしょうし、まだ若い方であれば大きく舵を切った方がいい場合もあるでしょう。
ということで、1つめは「新卒でいきなり大企業」でした。
20代は、「食べたい」「買いたい」「持ちたい」という欲求がとても強い時期です。行動エネルギーは人生の中で最も高く、そうした動機がその人の支出を形作っていく側面があると思います。
もちろん「いい生活をしたい」という思いが仕事で稼ぐモチベーションにつながることもあります。しかし、自分の身の丈を超えて生活水準をどんどん上げていくことは、大きな資産を築く上での足枷になってしまいます。
例えば、給料が上がったタイミングで「もう少し良い部屋に住みたい」と家賃を上げたり、「車を買おう」「ブランド品を持とう」と財布の紐を緩める。そうした行動のすべてを否定はしませんが、「それって本当に必要?」と一度立ち止まって考えることが大切です。
生活水準を上げるのは簡単。お金を使えば済むから。ただし、一度上げた水準を下げるのは本当に難しい。グレードを下げるという行為は、どこか“負け”のように感じられてしまい、心理的側面からなかなか元に戻せないからです。一度贅沢を覚えると戻れない、つまり生活水準は不可逆であるという前提で捉えておく必要があります。
生活水準を上げると身なりも良くなりますから、周囲から「あの人はお金持ってそうだ」と見られるようになります。その優越感が心地よく、ついそれを維持したくなってしまう。これが「見栄」というやつですね。
でもよく考えてみてください。見た目が華やかで、住む場所も一等地に見える人が、本当にお金持ちとは限りません。確かに収入(P/L)は高いのかもしれませんが、資産(B/S)で見ればむしろマイナスというケースだって珍しくありません。こうした背伸び、以前に紹介したこちらの回『「残クレアルファード」について思うこと』にも通じる部分があります。

本当の富というのは他人に見せびらかすことではなく、資産を育てていくことで心も豊かになること。浪費ではなく投資へ。ここを重視できるかどうかが将来の分かれ道になると思います。
ということで、2つめは「生活水準を上げる」でした。
これは会社員だから、組織の中にいるから、という話に限りません。プライベートにおける勉強でも趣味でもそうですが、「自分の力だけでなんとかやり切ろう」「一人で達成しよう」と思っても、実際に良い結果が出ることはそう多くありません。なぜならば個人でできる努力にはどうしても限界があるから。
世の中にはすでに“先人の知恵”がたくさん転がっています。会社で新しいプロジェクトに参加するにしても、趣味や資格の勉強を始めるにしても、必ずその道に詳しい人がいるものです。そういう人たちにアドバイスを求めたり、事例を聞いてみたり、似たケースを調べてみたり。そうした「他人の経験を借りてブーストをかける」ことを、どんどんやった方が良いです。
ぼく自身、この「やわらか中学校」の運営は一人で行っています。テーマ決めから原稿執筆、音声収録、スライド作成、動画編集まで、一貫してやっているわけですが、その源泉となっている資産形成の型は、多くの先人たちのブログやYouTube、書籍を元に形作られています。
そして、配信した動画のコメント欄でいただく皆さんの意見や感想から多くの気づきを得ていますし、それが次の企画や改善のきっかけになることも多々あります。まさにそれが“集合知”の力ですよね。自分の中の引き出しだけで考えるよりも、確実に質の高い結果につながります。
人は誰しも、自分以外の誰かから影響を受けて生きています。両親、先生、上司、同僚、友人。そうした存在が、自分の考えや行動を変えるきっかけになった経験が誰しもきっとあるはずです。だからこそ「自分の力だけでなんとかしよう」と意地になるより、素直に他人の知恵を取り入れていく姿勢が大事です。
今はネット社会で、情報を一瞬で調べることができます。これは大きな利点ですが、同時に“粗悪な情報”も溢れています。だからこそ、情報の“目利き力”も問われます。
さらに言えば、情報を取り過ぎるのも問題。知識を無限に入れ続けると、逆にどうすればよいか分からなくなり行動ができなくなるから。大切なのは「自分は何を達成したいのか」という目的に照らして、必要な情報を取捨選択すること。目的から逆算して行動する、それが本当の意味で“自分の力を最大限に活かす”ということだと思います。
ということで、3つめは「自分の力だけでなんとかする」でした。
これは、ぺいぱ自身もそういう時代があったので、あえてお伝えしたいと思います。
「自分はだいたい分かってるから」「それもう知ってるんで」といった感じで、情報を遮断したり、行動を止めてしまうことってあると思うんですよね。ぼくも30代のころ、まさにそういう時期がありました。
何度か話してますけど、資産運用でいえば日本株を始めた2004年。当時は遊び半分のデイトレまがいのことをして、100万円ほど損失を出しその後2007年にやめてしまいました。
「上がるか下がるか分からない投資なんかよりも、現金をコツコツ貯めていく方が正義だよね」と思い込み、結局その後10年間も投資から遠ざかってしまった。自分自身で将来の可能性を閉ざしてしまったわけです。
「投資とかそういう情報は耳にしない」「どんな話を聞いても自分の決断は変わらない」「もう十分どういうものかを理解した」という思い込み。たった4年、ちょっとかじっただけなのに全部を理解した気になっていたわけです。こういうことって、世の中にたくさんありませんか?
そういった傲慢さのせいで、自分ではまったく気付かないうちに損をする、新しいチャンスを見落としてしまう。自分が知っていることなんて、氷山の一角にすぎません。むしろ知らないことの方が圧倒的に多い。だからこそ、常に謙虚でいることが大事です。
どんな分野でも成功している人に共通しているのは、みんな謙虚だということ。謙虚だからこそ、自分の知らないことを貪欲に学び続けられる。人に頭を下げて教えを乞うことができる。最終的には、その「貪欲に学び続ける力」こそが、資産を引き寄せるエンジンになるんだと思います。
「なんとなく知ってる」「単語だけ聞いたことある」。そうやって分かった気になってしまうと、それは自分の成長を止めてしまうことになります。そして一度その状態に陥ると、自分を変えていくことが難しくなってしまう。うまくいかないことを周りや環境のせいにしてしまう。
だからこそ、すべての要因は自分にある。この考え方を持つことが大切です。ぼくは自分の知らない世界や分野に対して、これからも貪欲であり続けたいと思います。
ということで、4つめは「傲慢になる」でした。
人って自分自身の環境を「変わること」「変わらないこと」で天秤にかけたときに、どうしても“変わらない方”を大事にしてしまいます。少し不満や嫌なことがあったとしてもこのままであれば生きていくことはできる。人の持つ生存本能がそうさせるのかもしれません。
ぺいぱ自身も、20代より30代、そして今の40代と、年齢を重ねるごとにその傾向が強くなっていると感じます。今の環境に満足していなかったとしても、大きく変えることには抵抗がある。 変えようとすれば、新しく覚えること、用意すること、意識しなければならないことが増えて、正直めんどくさいから。だから、今のスタイルのまま放置してしまう。これが“現状維持”の罠です。
いわゆる「コンフォートゾーン(安心領域)」とも言われますが、ここに居続けるとたしかに大きな失敗はしないかもしれない。でも、大きな成功もない。
ロールプレイングゲームで言えば、最初の街の周りだけでレベル上げをしていても魔王は倒せません。少しずつ未開の地を進み、情報を仕入れ、強敵を倒し、アイテムを手に入れて、主人公を成長させていく必要があります。もちろん、尖ったやり込みとして最初の町付近でレベルをカンストさせることは物理的に可能ですが、尋常じゃなく膨大な手間と時間がかかります。
要は、見慣れた景色、見慣れた人、見慣れた結果に安心してしまうと、人生そのものが停滞していくんですよね。だからこそ、心地よい場所を“あえて壊していく”ことも大事だと思います。
不安や恐怖を感じる方向にこそ成長とチャンスがある。人生はまさにロールプレイングゲーム。一歩、二歩と知らない場所に踏み出していくことで、自分の可能性はどんどん広がっていくんだと思います。ぺいぱ自身も、これまでいくつかのチャレンジをしてきました。
たとえば株式投資。2020年に投資信託やETFという存在を初めて知り、翌年2021年に投資先を個別株からオルカン(全世界株式)一本に絞りました。これは自分にとっても大きな決断でありチャレンジでした。
当時はハイパーグロース株を中心に持っていて、うまくいっている銘柄も多かったので、「このままでいいんじゃないか」という葛藤もあったわけです。でも、あえて方向転換してシンプルにした結果が今につながっています。
同じように、ブログやYouTubeを始めたのも大きな挑戦でした。2020年から21年にかけてこの「やわらか中学校」を立ち上げたのも、自分にとって未知の世界への一歩。自分の資産形成の記録を残していこうという思いからスタートしましたが、今ではそれが視聴者の方々に行動するきっかけを与えていたりもするわけです。これは本当に自分の世界を広げるきっかけになりました。
そして、昨年会社を辞めたこと。これもまた大きな決断でした。50代が近づく中での早期退職。メイン収入が途絶えるわけですから不安も当然ありました。でも、退職で生まれた時間を使って新しいことに挑戦できた。脚本を一から学び始めたり、ゲーム実況をやってみたり、4コマ漫画の連載を始めたり。会社員時代の延長線上にはない新しい世界に飛び込むことができたわけです。
そうした中で得た経験や刺激は最終的に、精神的にも資産的にも両面の豊かさにつながっています。ですので、今の生活に安心感を覚えている人ほど、あえて新しいことを一つでも始めてみる。それが人生をもう一段階ステップアップさせるきっかけになるんじゃないかなと思います。
ということで、5つめは「現状にとどまる」でした。
おしらせ
キャラクター”ぺいぱ”がデザインされた「資産運用学園やわらか中学校」公式アイテムがついに販売開始!トイレットペーパーを模したキャラデザの由来は、古くなったお札が再利用されてトイレットペーパーになることや、ウン(運)がつく縁起ものだからなど、諸説あり。いずれのアイテムも日常使いできるシンプルデザインです!ぜひお買い求めください!

さいごに
ということで今回は「億り人を遠ざける5つの罠」をテーマに話を進めていきましたが、いかがだったでしょうか?
今回お話しした内容は、ぺいぱ自身の経験をもとにした振り返りであって、決してこれが唯一の正解ではありません。
しかしながら、「こうすればうまくいく」という“やることリスト”よりも、「これだけは避けよう」という“やめることリスト”の方が、実は資産形成においては大事だし、万人に当てはめやすいんじゃないかと思います。
今回挙げた5つの罠を意識しておくだけでも、資産はもちろん、ご自身の成長にも何かしらつながっていく、富を築いていくための土台になる、そんなふうに言えるかもしれません。
皆さんはこれまでの資産形成を振り返って「これは罠だな」と感じたエピソードはありますか? ぜひコメント欄で紹介してもらえると嬉しいです!
この「やわらか中学校」ではお金や仕事に関する話題を中心に、FIRE生活に突入したぺいぱの日常を赤裸々にお届けしています。ぜひチャンネル登録・いいね・コメントをよろしくお願いいたします!
また、YouTubeサブチャンネル「ぺいぱのひとりごと」は、ぺいぱが興味関心のある話題を取り上げて好き放題喋り倒すラジオのようなライブ配信番組となっていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
人生はノーコンティニュー!悔いのないようにやっていきましょう。
では、ごきげんよう。
謙虚さと貪欲さと心強さと。
:
:
:
:
:
メインテーマをひとしきり喋り終わった後で、さらになんやかんやと喋っていくコーナーです。
今回は億り人への道が1つのテーマだったわけですが、資産形成をしている方々がなんとなく頭の片隅に置いているのは、野村総研が隔年で発表している富裕層ピラミッドではないでしょうか。
この「やわらか中学校」でも、節目節目で取り上げてきていますが、直近だと2025年2月にお届けした回「2023年版 富裕層ピラミッドに見るアッパーマス層の二極化」です。

この調査は、預貯金・株式・債券・投資信託・一時払い生命保険や年金保険など、世帯として保有する金融資産の合計額から負債を差し引いた「純金融資産保有額」を基にし、総世帯を5つの階層に分類、それぞれの世帯数と純金融資産の合計額を推計したものです。
・超富裕層(5億円以上)
・富裕層(1億円以上 5億円未満)
・準富裕層(5千万円以上 1億円未満)
・アッパーマス層(3千万円以上 5千万円未満)
・マス層(3千万円未満)
そのため、主に流動性の高い資産の保有状況を広い括りで示したものとなりますので、資産状況の一側面に過ぎない点には注意が必要です。なお、ぺいはこの基準でいくと6,000万円ちょいなので準富裕層にあたります。
2025年2月発表の調査結果は前回(2年前)と比べると
・「準富裕層」以上の増加ペースが圧倒的
・「アッパーマス層」の減少が顕著
・「マス層」は増加しているが資産は大きく増えていない
こんなことが言え、株高が続いたこの2年間で資産を運用に回している層とそうでない層とに二極化している様子が見えてくるわけです。
このあたりの細かい解釈は当該回を参照いただくとして、そもそも現金の価値低下とそれに伴う資産バブルのような状況下にある中、先ほどの5つの階層区分に少し違和感が出ている側面ありますよね。要は「1億円で果たして富裕層なのか?」ということです。
もちろん統計というのは大前提として、区分名称がどうであるかより、記録の継続性を維持することの方が重要です。野村総研のこの調査は2005年から同様の形式で行われているからこそ、この20年間の推移や傾向を読み取ることができるわけです。これを時代に合わせてコロコロと統計の組み方を変えてしまっては役に立ちません。
この富裕層ピラミッド、世の中には不動産持ちも多くいる中で純金融資産という馴染みのないまとめ方だとか、野村総研の営業資料にすぎないとか、そういう声があることをまるっと飲み込んだ上での雑談になるわけですが、1億円なんてまるまる4%で運用しても400万円。ぼくのような独身クソ野郎が細々活きていくのでギリギリじゃないでしょうか。とても富裕層という言葉の響きから連想できるような生活ではありません。
では、言葉の持つイメージを改めて整理してみましょうか。あくまでぺいぱはこんな感じに受け取ってるというものです。ぜひ、皆さんもご自身で想像を膨らませてもらえればと思います。
【超富裕層】
海外と日本を行き来する生活。資産運用は専門チームに任せ、時間が何よりも大事。身の回りのものはオーダーメイド。「人類」とか「社会」を変えていく行動に情熱を注ぐ。
【富裕層】
都心の一等地に自宅を構え、休日は会員制ラウンジで食事。子どもの教育や健康にも惜しまず投資。お金を「使う」より「どう活かすか」を常に考え、節税にも熱心。
【準富裕層】
共働きで堅実に資産形成。投資は国際分散型、車は国産高級モデル。住宅ローンは完済し、老後資金の計画に余念がない。資産推移を見るのが日課。
【アッパーマス層】
老後2,000万円問題を常に意識。ふるさと納税・ポイ活・NISAを駆使して生活を最適化。日常の会話に「インフレ」「利回り」「節約」がよく登場する。
【マス層】
物価上昇を実感しつつ、節約と小さなご褒美でバランスを取る。給料日前はスーパーの特売チラシが心の支え。投資は気になるけど、まずは貯金が最優先。
これらの勝手なイメージを踏まえて資産額区分を再構成するとこんな感じでしょうか。
・超富裕層(10億円以上)
・富裕層(5億円以上 10億円未満)
・準富裕層(1億円以上 5億円未満)
・アッパーマス層(5千万円以上 1億円未満)
・マス層(5千万円未満)
5つではなくもう少し階層を細かくしてもいいような気もします。これだとほとんどがマス層に分類されてしまいますので守備範囲が広過ぎるだろという感じがする一方、そもそも「マス」というのはそういうものだとも言えます。まぁ、なかなかしっくりくる分け方って難しいですね。
いずれにしても野村総研が調査を開始した2005年時点ではたしかに1億円以上あれば富裕層というのは、本当にそうだったのかもしれません。この20年で、
・金融緩和による資産価格上昇
・給与所得の伸び悩み
・金融リテラシーや投資行動の差
このような背景とともに、実態と「富裕層」という言葉のイメージが、少しずつずれてきているんだと思います。
ということで、皆さんは肌感覚として富裕層ピラミッドの5階層、どんな感じだと思いますか? ぜひそれぞれが今最もしっくりくるピラミッド区分を教えてください!
では、ごきげんよう。